個で上回っていたセネガルの誤算。日本のビルドアップの高度な工夫

林舞輝の日本代表テクニカルレポート第2回:日本対セネガル
欧州サッカーの指導者養成機関の最高峰の一つであるポルト大学大学院に在籍しつつ、ポルトガル1部のボアビスタU-22でコーチを務める新進気鋭の23歳、林舞輝が日本代表のゲームを戦術的な視点から斬る。第2回のテーマは、難敵セネガル相手に優勢に試合を進められた決め手となった「日本のビルドアップの高度な工夫」について検証する。
正直に言えば、フットボリスタ本誌に寄稿した私のセネガル戦の分析とシミュレーションは間違っていたと言わざるを得ない。理由は簡単で、クリバリ&サネという世界最高クラスと言っても過言ではないCBコンビ相手に大迫がボールを収められるとは思っていなかったし、セネガルの屈強なFW陣相手に昌子が競り勝てるとも思っていなかったし、圧倒的な突破力のある両ウイングを酒井&長友が封じられるとも思っていなかった。だが、蓋を開けてみればすべての局面で勇気を持って互角に渡り合い、その局面でのエピソードを紡いで一つのストーリーを作った柴崎という圧倒的な存在がいた。つまり、分析の前提そのものが間違っていたのだ。もしかしたら、それはセネガルも同じだったのかもしれない。
失点の裏にあったセネガルの狙い
セネガルは日本の[4-2-3-1]に噛み合わせた[4-3-3]で挑んできた。開始直後はスピードとパワーを生かした果敢なハイプレスで機先を制しにくる。観ているこちらはハラハラするような互いのゴール前を行き来する展開になるものの、日本の選手たちは至って冷静だった。“猫だましプレス”には動じずに応戦、ポゼッションを高めることに成功した。
が、ようやく試合が落ち着いた頃に失点。クロスに対して原口が対応を誤り、川島がパンチングを目の前にいたマネに当ててしまう。致命的なミスであることは明らかだが、原口は日本が高さで圧倒的に劣る以上なるべくCKを避けたいという心理が働いたこと(もしくはCKはできるだけ回避しろとのスカウティングがあったかもしれない)、川島は目の前にマネが詰めているのが視界に入りとっさに複数の選択肢が頭をよぎったことを考慮するべきだろう。
もっと言えば、格上のセネガルに真っ向勝負をしている以上、サイドの局面を攻略され、逆サイドへのハイクロスに原口がペナルティエリア内まで戻って対応せざるを得ないという状態になってしまった時点で、問題があった。左の乾も自陣で引いた時の守備には難があり、右の原口は戻っては来るが対応があやふやなケースがあるため、セネガルはマネのサイドよりも「右ウイングのサールからの崩し→逆サイドのマネでフィニッシュする形」を最初から狙っているようだった。
キーマンは昌子、[3-3-3-1]で翻弄
序盤の“猫だましプレス”の後、セネガルはミドルゾーンでの[4-4-2]のプレスに切り替える。相手SBをボールの奪いどころに設定することが多いセネガルだが、日本は長友のところで詰まってボールを失った以降、SB経由のビルドアップと前進を意図的に回避。長谷部が吉田と昌子の2CBの間に下がり、3人で後方でのボール回し始める。
ここでセネガルは明らかにボールを昌子に誘導するような追い込み方をしていた。おそらく、唯一Jリーグでプレーする昌子が吉田よりビルドアップ能力に劣り、利き足と逆側のサイドのCB(昌子は右利きだが左CB)であることを理由に、試合前から決めていたことだろう。だが、ここがまずセネガルの誤算だった。昌子はボールを運んだり、少ないタッチで預けてからもらい直したり、相手のプレスを翻弄。この試合のビルドアップのキーマンは昌子であり、見事にそのタスクをこなした。

結果、セネガルのパパ・エンディアイェ(ブロック守備時はインサイドMFからFWへ移動)はポジショニングがどんどん曖昧になっていく。単に疲れたからハイプレスをやめたのか、行っても取れないから精神的に下がったのかはわからないが、プレスのスイッチのかけ方に原則はなく、強度も落ちていった。
この攻防が、日本がこの試合でボールを回せる1つのキーとなった。この場合、パパ・エンディアイェは諦めずにCFと連動しながら日本のビルドアップ隊にプレスをかけ続けるか、後ろに戻って残り2人のMF(グイェ、アルフレッド・エンディアイェ)と組んでスペースを消すかハッキリするべきだった。だが、後方には下がらないし、連動した激しいプレスもかけない。

セネガルはゾーンに入ってきた選手を捕まえてマンツーマン気味に食いついて奪う原則があり、前述したように奪いどころを相手SBにしているので、両ウイングは日本のSBが外に開けば一緒について行こうとする。結果、香川と柴崎に中央でスペースが与えられ、それぞれ左と右のハーフスペースを主戦場にしながらボールを引き出した。形としては[3-3-3-1](吉田―長谷部―昌子/酒井―柴崎(右ハーフスペース)―長友/原口―香川(左ハーフスペース)―乾/大迫)でボールを動かす。乾と原口は幅と深さを作りつつ外から中に入って受け、大外の裏をSBが狙う。
日本の同点ゴールでは、香川が下がって中央にスペースを空け、中に入った乾にセネガルの右SBが食いつき、空いた大外の裏に走りこんだ長友に柴崎が正確なロングボールを送るという、極めて理にかなった崩し方であった。
Goal analysis – #JPN x #SEN #JFA
Width and depth of the field – positioning of fullbacks in order to release halfspaces for CM +bCDM between CB – distance and support to attract. It’s also interesting to notice wingers movement in order to height of FB. @JFA @jfa_samuraiblue pic.twitter.com/3eX4468zLc— Mindfootballness (@slawekmorawski) 2018年6月25日
香川と柴崎の「ハーフスペース」&「ライン間」攻略
試合を通して、前線の各選手が人の動きに釣られて空いたスペースを利用して、人の間とゾーンの間でボールを受けキープできたことが大きい。セネガルは人に食いつく守備をするので、ライン間を引いたり出たりの縦の動きに滅法弱かった。ゾーンに入った人を捕まえて潰す原則があるものの、完全なマンツーマンではないため、エリアからエリアへ縦に移動する選手に対してどこまでついていくか、どこから他選手に受け渡すかが曖昧になってしまっていた。
香川が引いて相手を食いつかせ、空いたスペースに原口&乾が中に入り、大迫がDFとMFのライン間で縦パスを受けに入る。日本の吉田、長谷部、昌子のビルドアップラインも大迫まで正確な縦パスを通すことができ、大迫は足下にボールがキッチリ入れさえすれば収められていた。まともにデュエルをしたら身体ごとボールを狩り取られるであろう日本は、これこそが狙ったポゼッション方法だったのだろう。ボールを受ければ各局面で各選手たちがひるまず勇気を持って勝負を仕掛け、柴崎が適切な局面に適切なボールを供給しつつ対角の大外への正確なロングボールで相手の組織を分散。まさに司令塔と呼ぶにふさわしいものだった。

一方のセネガルは、ポジションチェンジもほとんど行わずリスクもかけない。試合を通してカウンターとニアングへのロングパスで試合を組み立てようとする。このロングボールに昌子が互角に渡り合うどころか普通に競り勝っていたのが非常に大きかった。
ボールを保持する日本と、構えてカウンターを狙うセネガル。後半、日本はカウンター制圧からの逆カウンターで柴崎のクロスから大迫、中央でタメた大迫から乾という2つの決定機を作る。だが、この試合で唯一と言ってもいい個とグループ・コンビネーションによる崩しからセネガルが再度勝ち越す。
「ストーリーメイカー」柴崎岳
リードされた日本は、本田、続けて岡崎を投入し[4-4-2]へ。本田をサイドに張らせることでボールの収まりどころをサイドに移行させ、岡崎が最前線でのアクションを増やしてそこからの崩しを狙う。結果的には岡崎が潰れて本田がゴールを決め交代策は的中。だが、それまでセネガルを苦しめていたエリアとエリアを移動する縦の動きは少なくなり、ボールを引き出すという面で質が落ちたことは覚えておかなければならない。ラフな展開が多くなり、攻撃から守備へ切り替わる時のポジショニングも崩れた。セカンドボールを次から次へと回収していく柴崎がいなければ、まともにカウンターを食らっていたであろうシーンが多々あったのも確かだ。

西野監督はラスト5分で最後の交代枠を宇佐美に使い、勝ちに行くメッセージを選手に伝える。グループで最も厳しいと思われる相手にリスクをかけて勝ちに行くという決断は賛否が分かれると思うが(普通の監督なら引き分け狙いに行くだろう)、最も重要なのは勝ちに行くのか引き分けでいいのかの意思を全選手で統率することであった。その点でこの交代が非常に有効だったのは、選手たちがスローインを躊躇なく素早くリスタートさせていたことからも見てわかった。
試合を通して、コロンビア戦に続き日本の個のクオリティが光った。強さと柔らかさと創意工夫でフィジカル勝負に勝った昌子と大迫(セネガルはまさか最前線でも最後尾でも空中戦で勝てないとは思ってもいなかっただろう)、長谷部を落とした安定したビルドアップの形、両サイドの攻防、ライン間を引いたり出たりを繰り返し局面で攪乱する前線、そして各選手の勇気とハードワークを結び付けチームにバランスをもたらした柴崎。柴崎は、遠藤のようにゲームを作りながら中村憲剛のようにチャンスを作り出し、ゲームメイカーとチャンスメイカーを合わせた「ストーリーメイカー」だった。それでいて、守備面では圧倒的なポジショニングと予測能力でセカンドボールを回収して相手のチャンスの芽を潰す、「ストーリーブレイカー」でもあった。

日本サッカーにとって「勝ち点1以上の価値」
コロンビア戦は「ツキ」の部分が大きくどうしても評価が難しかったが、今回ベスト8の実力があるセネガル相手に二度追いついて勝利の可能性すら示したのは、勝ち点1以上の価値があったと言って良いだろう。「勝てた」と感じたのは日本で、「やられた」と感じたのはセネガルの方だろう。フィジカルで劣る部分を他の要素で補うのではなく、フィジカルに対してフィジカルでまともに対抗するのがスタートラインでそこから他の要素で差をつけるという、過去の「自分たちのサッカー」以上に自分たちにふさわしいサッカーへの道筋も見つけた。コロンビア戦の勝ち点3は日本サッカーにとって3ほどの価値はなかったように思うが、セネガル戦でつかみ取った勝ち点1は1以上の価値があったかもしれない。
課題はいくつか見られたが、一番はファイナルサードでの守備があまりにも脆いということだ。ハイプレスとミドルプレスでは大迫と香川が非常に知的な守備で追い込み、サイドはサイドMFとSBが連携してコースを限定しながら挟みに行くなどの連携守備ができるものの、低い位置でのブロック守備では決して固いとは言えない。判断ミスが多いように見えるが、それはつまり判断する際の材料となる原則が決まっていないということだ。
日本は試合を重ねるごとにボール保持時のプレー原則はでき上がっているものの、守備面、特にファイナルサードでの守備はまだまだあやふやな部分が多く、それにより「考えて判断しなければならない」という判断ミスのリスクがある。おそらく、西野監督は「そもそもファイナルサードで守らなければならない回数を減らせばいい=ボール保持の質を高める」という策を最優先するように思えるが、そうは言ってもサッカーをしている限りラスト30mまで運ばれる場面は必ず訪れる。そうした最後の守備の局面では切羽詰まって余裕がないのが普通である以上、判断の基準となるような「こういう時はこうする」というある程度の原則があれば、少なくとも初歩的な判断ミスは避けられる。
正直、すでにグループステージ敗退が決まったポーランドがどのようなメンバー、どのようなモチベーションで試合に臨んでくるかはわからない。ただし、2敗しているとはいえ個でも組織でも格上なのはポーランドだ。大迫はレバンドフスキではないし、川島はシュチェスニーではない。ここで落とせばコロンビア戦とセネガル戦のすべてが台無しになるかもしれない。今一度、このセネガル戦で見せた挑戦者の心構えを忘れず、最高の集中力を見せる時だ。
Photos: Getty Images
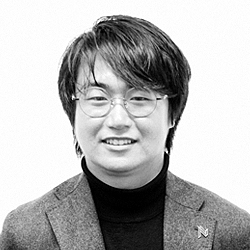
Profile
林 舞輝
1994年12月11日生まれ。イギリスの大学でスポーツ科学を専攻し、首席で卒業。在学中、チャールトンのアカデミー(U-10)とスクールでコーチ。2017年よりポルト大学スポーツ学部の大学院に進学。同時にポルトガル1部リーグに所属するボアビスタのBチームのアシスタントコーチを務める。モウリーニョが責任者・講師を務める指導者養成コースで学び、わずか23歳でJFLに所属する奈良クラブのGMに就任。2020年より同クラブの監督を務める。









