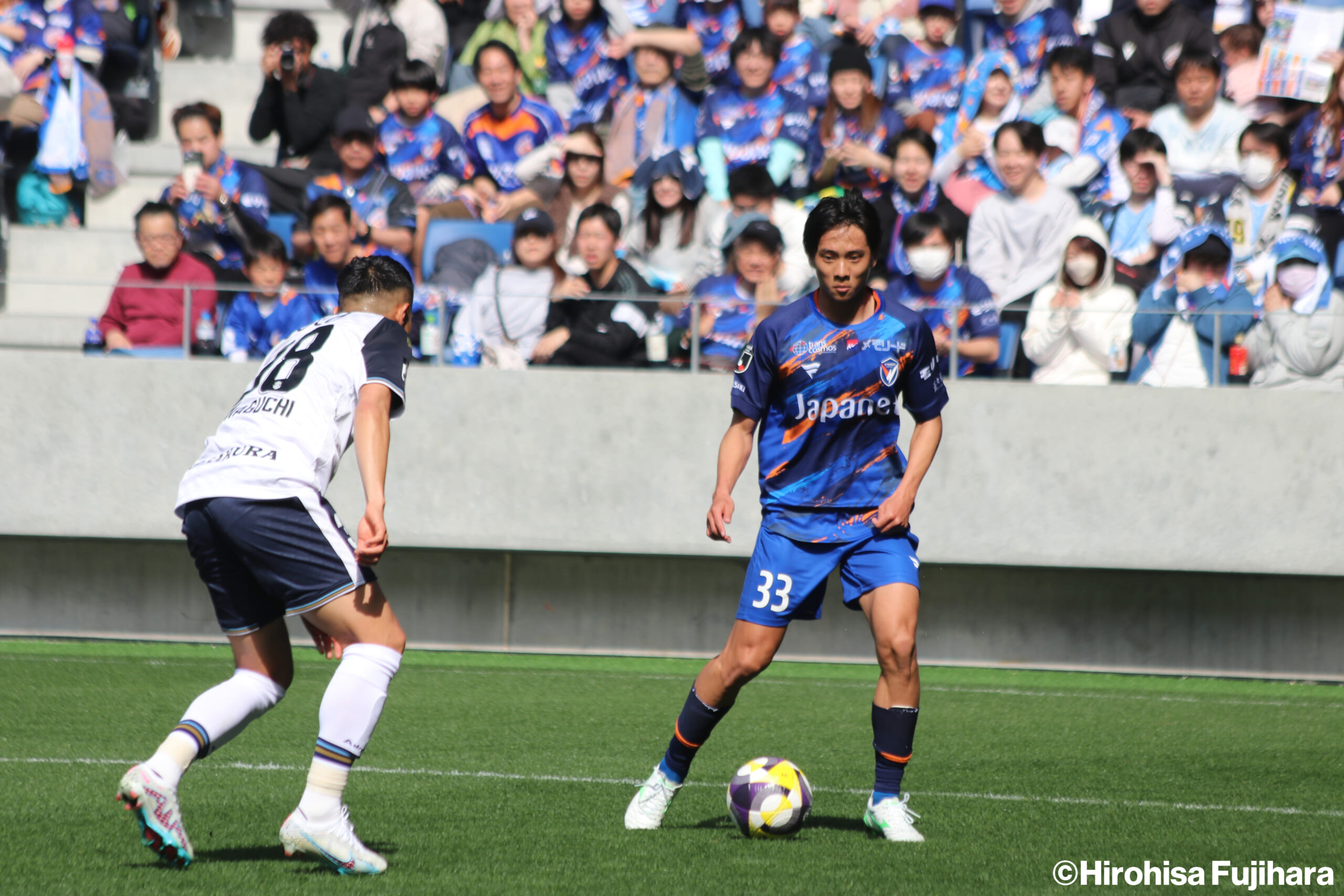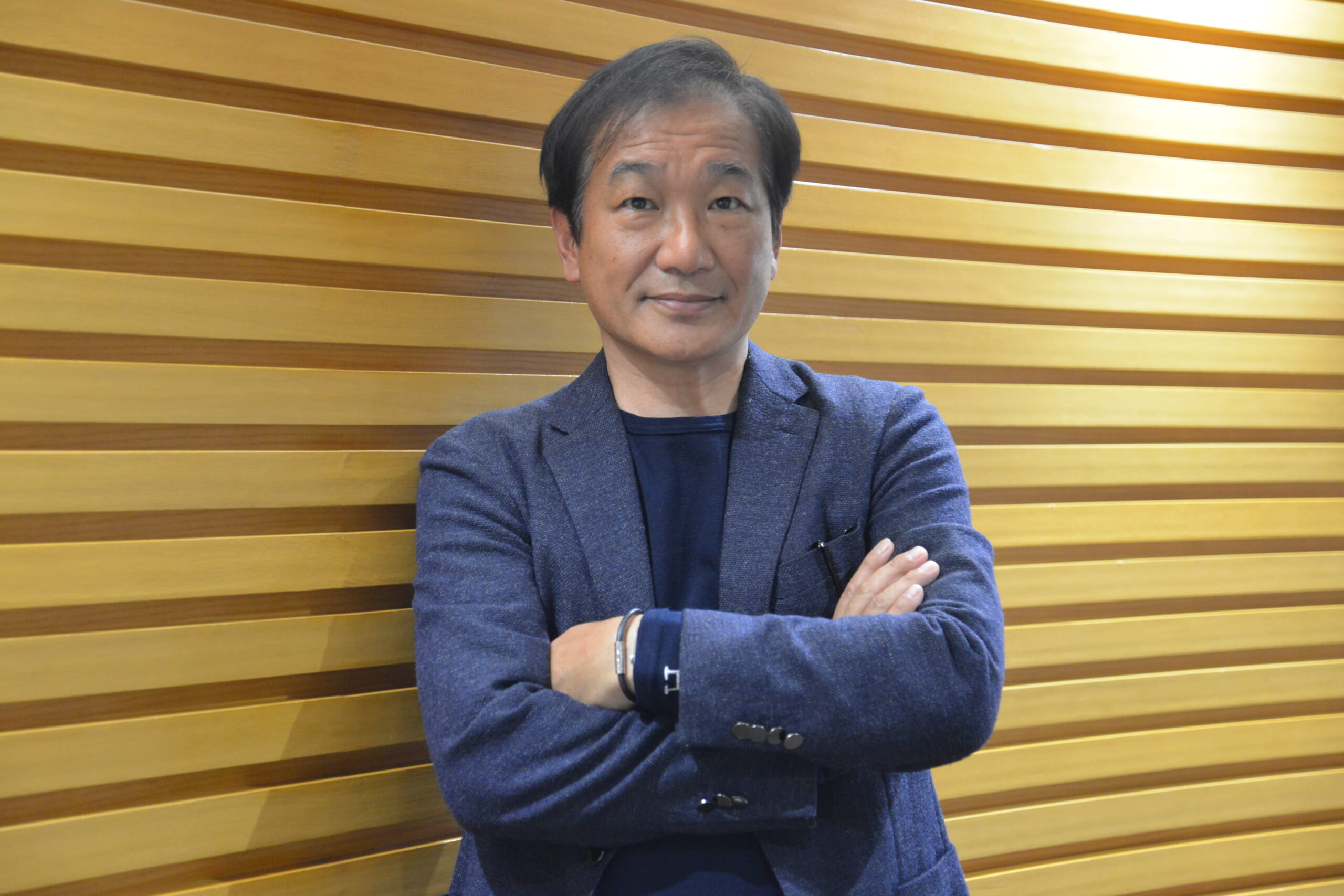
JFAの技術委員長を務めた後、レノファ山口、ベトナムのサイゴンFC、大宮アルディージャの監督を歴任した後、2023年から2年間、松本山雅の指揮を執った霜田正浩。日本と海外、現場と強化の両方を知る稀有なキャリアを歩む58歳に、松本山雅での挑戦の舞台裏、国内外の戦術トレンド、そして指導論について聞いた。
後編では、サッカーを取り巻く環境の変化がもたらした諸々の変容=戦術トレンド、監督の仕事、そしてZ世代への指導論についての興味深い解釈を教えてくれた。
5人交代、インテンシティ向上、GPSで何が変わったのか?
――せっかくの機会なので、最近のサッカーの変化についても聞かせてください。5人交代ルールによって主力級を温存して後半にぶつけるなども可能になり、戦略・戦術の幅が明らかに変わってきていると感じています。現場の実感としてはいかがでしょうか?
「後半勝負が戦略の1つとして定着しましたよね。もちろん、先に点を取って時計の針を進めていくプランもありますが、『今日は固い試合になりそうだな』とか『大雨でピッチコンディションが悪くて慎重な試合になるな』とかであれば後半の1点勝負になる可能性が高いので、あえてベンチに切り札を残しておいて、どういうタイミングで入れるかを考えるというのは、当たり前の戦略になってきていると思います」
――そうなってくると、ベストメンバーの定義も曖昧になってきますよね。
「レギュラーと言えるのは絶対変えられない5人で、あとの5人は戦略次第という捉え方がいいのかもしれませんね。肉体的な疲労やケガの交代だけではなく、より戦術的な交代がしやすくなりました。特にビッグクラブは2つのチームを持つようになっています。どちらがAチーム、Bチームではなく、相手やスケジュールによって組み合わせを変えていく。イタリアでは60分で必ず交代するチームがありますし、マスカット時代の横浜F・マリノスもそれに近かった」
――絶対変えられない5人もDFやGKで、変えるのは前の5人になりがちじゃないですか。そうすると、必ずしもレギュラーの方が上という見方すらできないのかもしれません。
「昔は『ハイプレスは90分間持たない』と言われていましたが、今の前の選手は90分間を考える必要がない。行けるところまで行って、疲れたら交代すればいい。途中から入った前線の選手が攻守にさらにギアを上げる。その結果、前からのプレッシャーはさらに強くなり、ゲームの強度が上がり、デュエルも増えてくる。選手のアスリート化がますます求められる流れになってきていますね」
――日本サッカーのインテンシティの変化はどう感じていますか? やはりかなり上がってきていますか?
「約10年前、僕が代表チームに携わっている時、ザッケローニもハリルホジッチも『Jリーグにはインテンシティが足りない』と言っていました。ところが今は、外国人監督からそう言われることがほとんどなくなりました。それが答えじゃないですか。今はプレーのインテンシティ、デュエルの強さが標準装備になりました。下のカテゴリー、J2やJ3も同じです。例えば、ルヴァンカップなどでJ1と当たっても強度面の差はほぼないです。個人のプレーのクオリティや判断の速さはJ1の方が高いですが、フィジカルの部分はみんな高いレベルが求められているので変わらないですね」
――今はGPSで最高速度やスプリント回数が可視化されるようになって、そうした数字が選手の評価にも直結するようになってきていますからね。
「ただ、数字で目に見えるようになりましたが、サッカーではそれがすべてではないですよ。時速35kmを出せる選手でも、いつ走ればいいかわからなければ試合ではそれを発揮できません。選手に求められるスペックはサッカースタイル次第で、時速35kmを出すことよりも自分の能力の使い方、サッカーIQと言われる頭の部分が試合の中では重要だと思います」
現場で使える「分析」とは何か
――近年のJリーグのもう1つのトピックとして「アナリスト」という職業の認知が上がってきています。対戦相手の分析が重視されてきていることの表れだと思いますが、霜田さんの分析に対する考え方を教えてください。
……

Profile
浅野 賀一
1980年、北海道釧路市生まれ。3年半のサラリーマン生活を経て、2005年からフリーランス活動を開始。2006年10月から海外サッカー専門誌『footballista』の創刊メンバーとして加わり、2015年8月から編集長を務める。西部謙司氏との共著に『戦術に関してはこの本が最高峰』(東邦出版)がある。