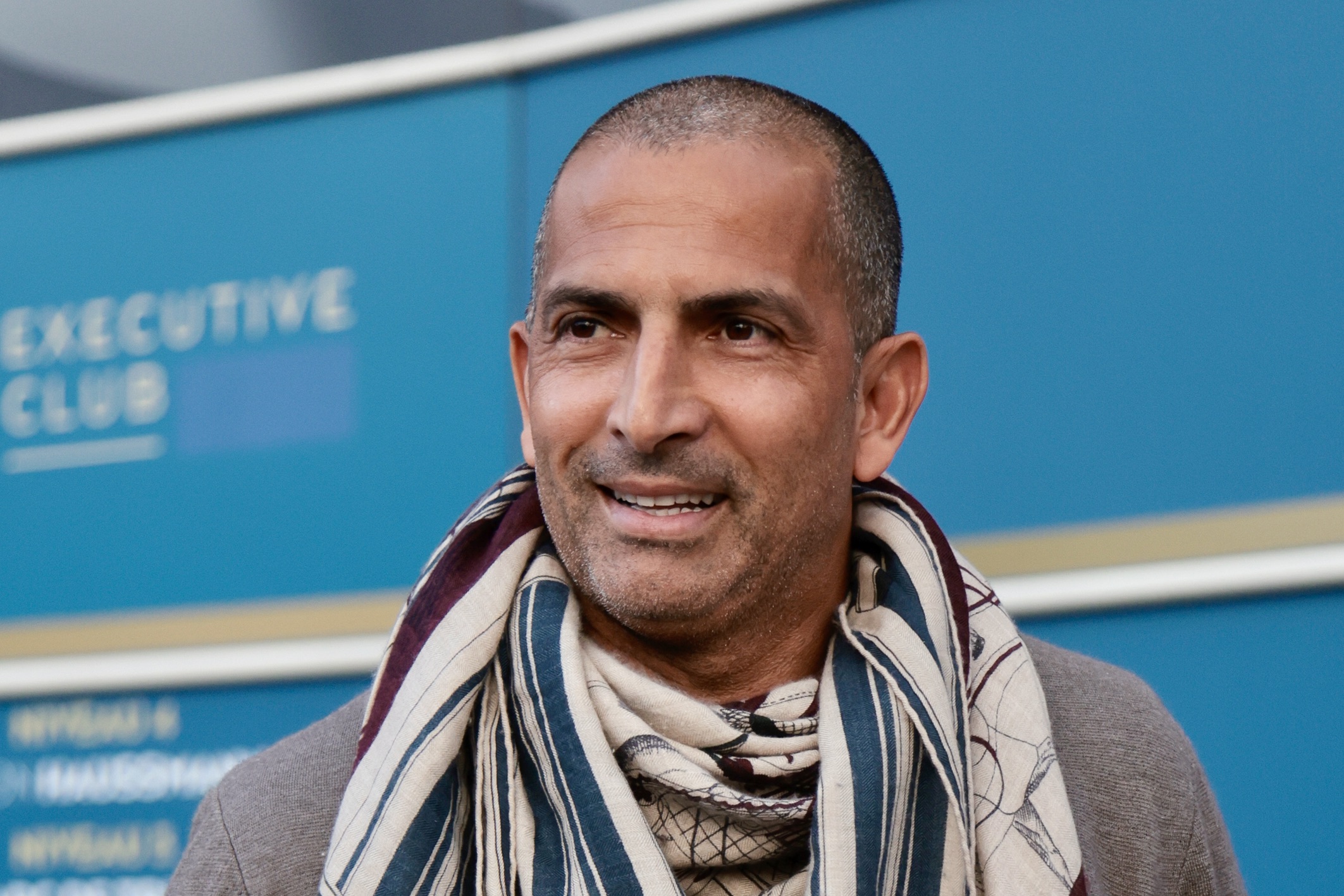新戦力不発を久保投入で誤魔化せなかったオーストラリア戦。日本の最終予選初黒星をどう受け止めるべきか?

世界最速で北中米W杯予選突破を確定させた3月シリーズから、27人中14人ものメンバーを入れ替えて6月シリーズを戦っている日本。その初戦として9人が今アジア最終予選初先発を果たすも不発に終わった第9節オーストラリア戦での初黒星をどう受け止めるべきか?『森保JAPAN戦術レポート 大国撃破へのシナリオとベスト8の壁に挑んだ記録』の著者、らいかーると氏と考えてみよう。
史上最速でW杯出場を決めた日本。本大会のポッド分けにも響くため、消化試合になっても北中米W杯アジア最終予選では結果を求められる説もあった。しかし多少の余裕があるのか、第9節オーストラリア戦のスタメンには、フル代表にあまり馴染みのなかった顔ぶれがずらりと並んでいる。本番を見据えて掘り出し物を探す旅に出るのだろう。オーストラリア相手の実戦で出場機会の少ない選手の経験値を上げることができるなんて、しばらくは訪れない格好の機会なのではないだろうか。
4年前を思い出してみると、カタールW杯アジア最終予選を突破した日本代表は守田英正、田中碧の起用によって生み出された[4-3-3]の発展に勤しんでいた。その過程の中で、多くの選手がインサイドハーフで試され、彼らの個性をどう生かすかよりもその戦術をトレースできるかどうかを優先的に実験していた記憶がある。この6月シリーズも招集メンバーの特徴を生かす配置ではなく、継続してきた猫も杓子も[3-2-5]で試合に臨むところは重なる流れと言えるだろう。
北中米W杯でもアタッカーのウイングバック起用を継続するのか、逆により守備的な選手と入れ替えるような調整が入るのか、前回の[4-3-3]と同じように途中で打ち切りとなるかは今後注目していきたいポイントとなる。
相手のウイングの裏と脇を狙う中盤のポジションチェンジ
オーストラリアのキックオフはCB町田浩樹が守る左サイドにロングボールを蹴るふりをして、後ろからパスを繋ぐという奇襲であった。驚いたであろう中でも、右CBの関根大輝が冷静に相手との1対1を迎撃で対応して戦いの幕が開ける。日本は相手の[3-4-3]と配置が噛み合うことも相まって、彼ら最終ラインがどれだけ数的同数を受け入れられるかどうかがテーマとなった。ファーストプレーでその一問目を乗り越えられたことは心強かったのではないだろうか。
前回対戦では日本の3バックでのボール保持に対して、3枚でパスを繋ぐならプレッシングに行きつつ、中盤が降りて4枚になるなら様子を見てきたオーストラリア。しかし、今回はボール非保持の配置こそ[5-2-3]だけれども、相手のDFラインがボールを持っても放置気味。日本としてはCBがオープンな形でボールを持てるので、セントラルハーフも降りる必要はないと判断したのではないだろうか。
自陣では[5-4-1]にはっきりと変更する2位オーストラリアは、むしろ守備意識の高さを感じさせてくる。勝ち点は+4、得失点は+9の差をつける3位サウジアラビアとの直接対決が待つ最終節を前に、引き分けでもOKという考えがあったのかもしれない。もしくはトランジション合戦になった場合にどうなるか、未知数だったこともあるのだろう。いっそのこと日本にボールを持ってもらった方が、予測を立てやすくなるという、わかりやすいゲームプランだったのではないだろうか。
それでも日本からすれば想定の範囲内だったのだろう。2シャドーの鎌田大地と鈴木唯人を相手の両ウイングの背中に立たせることで、オーストラリアの守備網を広げようと画策。ついでに彼らをビルドアップの出口にできるおまけつきの立ち位置となった。次の手は右ボランチの藤田譲瑠チマの大外への移動と、最終ラインの枚数を増やすことで生まれる噛み合わせのずれよりも、中盤の移動による撹乱を計画していたかのような印象を受ける。
ゴールキックも繋いでいくオーストラリアを見ていると、キックオフがブラフでなかったことがわかる。対する日本のプレッシングは強烈の一言で、時間の経過とともにオーストラリアはボールを持てないまま自陣に押し込まれていく。そして活発に行われているのがMFのポジションチェンジ。鈴木と鎌田が移動すれば、藤田と左ボランチの佐野海舟が前に出る形は練習通りなのだろう。惜しむらくは背後への飛び出しに対してボールが出てこないこと。小野伸二解説員の言葉を借りれば、「目がそろっていない」ということだろう。新戦力の同時投入におけるデメリットだが、しょうがないことはしょうがない。
序盤で最も目立っていた選手は初召集で左ウイングバックを任された俵積田晃太だろうか。サイドからの積極的な縦突破から、クロスにはあまり可能性を感じなかったが、自身の特徴を出すことには成功していた。なかなか自陣から出られないオーストラリアは、日本のスローインやゴールキックによる再開を狙ってプレッシングを解禁する。しかしかえってウイングの背中と脇を狙い続ける相手の中盤に、ビルドアップの出口となることを許す格好となった。
10分にはゴールキックを蹴っ飛ばすオーストラリア。ボールを繋ぐふりをして相手を自陣深くに誘き寄せてからロングボールを狙う戦略というよりも、シンプルに日本のプレッシングの圧に屈しているだけのようだった。高さは彼らの専売特許だったが、アジア屈指のサイズになってきている日本のCBがロングボールにも負ける雰囲気はない。2006年W杯での記憶は苦いままだが、時代は移ろうものだ。
CB両脇も攻撃参加!ミシャ式を再解禁も惜しむらくは…
……

Profile
らいかーると
昭和生まれ平成育ちの浦和出身。サッカー戦術分析ブログ『サッカーの面白い戦術分析を心がけます』の主宰で、そのユニークな語り口から指導者にもかかわらず『footballista』や『フットボール批評』など様々な媒体で記事を寄稿するようになった人気ブロガー。書くことは非常に勉強になるので、「他の監督やコーチも参加してくれないかな」と心のどこかで願っている。好きなバンドは、マンチェスター出身のNew Order。 著書に『アナリシス・アイ サッカーの面白い戦術分析の方法、教えます』 (小学館)。