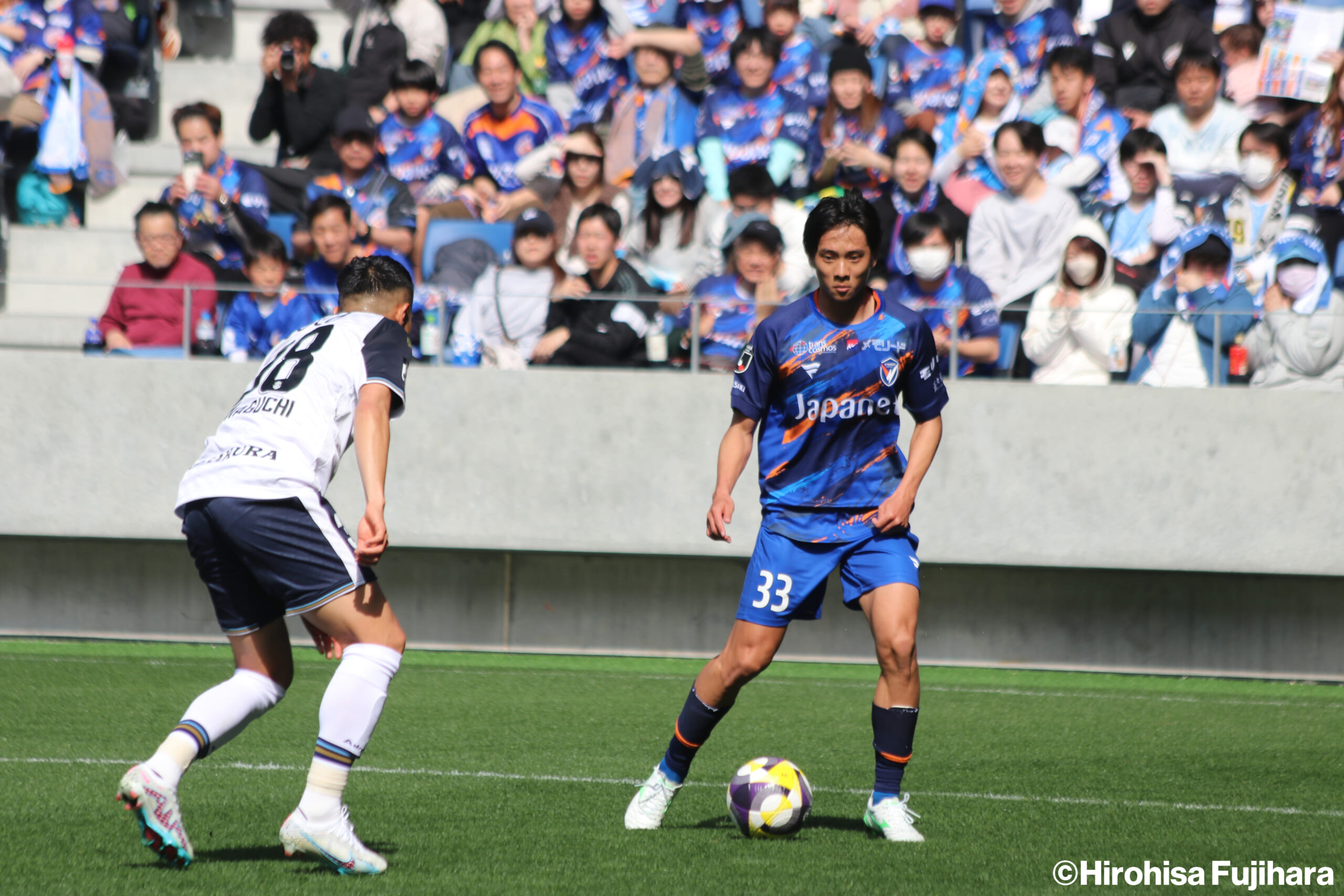2024年終盤戦の9連勝を導いた信念と策略。ディサロや土居の活躍前に掴んでいた手応えとは?【山形・渡邉晋監督インタビュー前編】

昨季のモンテディオ山形は序盤戦こそつまづいたが徐々に巻き返し、シーズン終盤には怒涛の9連勝でJ1昇格プレーオフ進出を掴んだ。夏の移籍で加入したディサロ燦シルヴァーノや土居聖真らの活躍に目を奪われるが、その内実に耳を傾けると確固たる信念によるチームビルディングが奏功したことがわかる。渡邉晋監督へのインタビューを通じて当時のチーム状況について深堀した。
すべては一昨年のプレーオフ清水戦の敗退から始まった
――昨シーズンは序盤につまづきましたが、尻上がりに勝ち点を伸ばし、終盤はクラブ史上最多の9連勝を飾って4位でプレーオフへ。しかし、最後は岡山に敗れて昇格を逃しました。昨シーズンについて、どのように総括していますか?
「まず、それを振り返る前にお話しなければいけないのは、一昨年(2023年)のプレーオフ、清水戦のことです。あのゲームは引き分けで、我々はプレーオフ敗退という結果に終わりましたが、自分たちがシーズンを通してやろうとしたこと、実際にできたことに関して手応えはあったし、ここまで出来るようになった、と感じたゲームでした。プレーオフに至るまでの終盤も、5連勝がありましたけど、僕から何かを提示するもの、引き出しという言い方をしましたが、その数が少しずつ増えていき、最終的に選手たちがその引き出しをどの瞬間に開けたらベストなのかを選べるようになりました。それが2023年の集大成というか、引き分けで終わったからダメなんですけど、内容としてそういうものは出せたと思っていました。
だからこそ、昨シーズン(2024年)はプレーオフ清水戦からの上積みとして、そこに何を足していくかを考えて準備をしました。『足す』と考えると、何かを落とし込んだり、植え付けたりを想像すると思いますが、逆に僕から伝えるものを削ぎ落とすことで、選手たちの発想を促し、結果的にプレーを足すものにしていくと、そういう逆説的な捉え方で準備をしていました。今まで僕が提示してきたものを手放し、彼らにもっと自由を与える。そのトライが必要と思っていて、より抽象的に物事を伝えたりしながら、『もっとあなたたちが選べるものはあるんだよ』『もっとすごい発想くださいよ』というアプローチで上積みをしつつ、2024年に臨もうとしました」
――なるほど。その辺り、ビルドアップやプレッシングなどで一例を挙げてもらえますか?
「ビルドアップで言うと、3枚になるか、それが右上がりか左上がりか。その可変だ何だという形のところを、2023年の途中に監督に就任したときは、明確に伝えるようにしました。そうすることでまず選手たちの引き出しを増やし、最終的には彼ら自身が試合中に選べるようになってきたのが、プレーオフ清水戦です。
その後の2024年は、3枚とか4枚とか、そういう可変の数字や形を一切言わない。トレーニングやゲームでも、『距離もうちょっと近づければ?』『ボランチもうちょっとリンクして』『つながれ』とか、リンクする距離やずらす距離といったところで、言葉の抽象度をあえて高めて、選手の裁量を増やすという感覚です。2024年はそのようなアプローチでキャンプからスタートしました」
昨季の序盤戦につまづいた理由
――確かに「3枚でビルドアップする」と言っても、ピッチ内ではその3枚の距離を狭くするのか遠くするのか、もしくは3枚のうち1枚だけは少しだけ高い位置を取ってずらすとか、同じ3枚でも相手のプレスの掛け方に応じて違いはありますよね。そういう部分、数字の向こう側で、調整を始めるようになったという感じでしょうか。昨シーズンの2024年の序盤は。
「そうです。昨年は新しいスタッフが数多く山形に来てくれたのですが、彼らが対戦相手として我々を見ていたとき、『山形は捕まえづらい』『分析しづらい』と、そういう印象を持っていたそうなんですね。それは間違いなく僕らの強みだと思っていたので、その部分をもっと出していけるようにと考えました。
そして、今仰ったような調整は、そもそも3枚の距離を理解していないとできないけど、2023年の終盤はここまでやれたから、もうわかっているでしょ、と。だったら、もっと自分たちで相手を見ながら思い切って寄ったり、離れたり、その距離感は工夫できるんじゃないか? やってごらんよ、というような捉え方でした。
実際にキャンプでも試してみて、悪い流れではなかったし、開幕から2試合は勝って、結果も付いてきた。ただ、その後はキーマンのポジションで、センターフォワードの藤本佳希とトップ下の後藤優介が怪我で出場できなくなり、ボランチの南秀仁も体調不良もあってコンディションを作れず、彼らを失ったところから崩れて、2連勝スタートの後に連敗が続くという流れになってしまいました」
――確かに、彼らの負傷離脱は痛かったですね。
「ただ、そのときに思ったのは、ちょっと土台を疎かにしてしまったかな、と。僕は一昨年のプレーオフ清水戦で手応えを得ていたので、もう土台は出来ているものとしての上積みだったけど、やっぱり核となる選手がいなくなったとき、立ち戻る場所をみんなで共有できていなかった。そして、シーズン中にそこに取り掛からざるを得なくなったことが、前半戦に苦しんだ原因でした。
その辺りを指摘してくれたのが、昨年に新しく入ってくれたコーチ陣(大分から岩瀬健、仙台から貝﨑佳祐、鹿児島から弓谷蓮)です。『ナベさんが言うリンクとか、つながれとか、意外と選手はわかっていないと思いますよ』『正直、僕らもどれくらいなのか具体的にはわかっていないから』と、序盤に苦しんだ時期にみんなで話し合って、彼らが率直に言ってくれたので、『そうだったのか』と自省することができました。
昨年は新しく山形に入ってきた選手も多かったので、彼らからすると『リンク』ってどういう意味なのか、『つながる』ってどれくらい近づくのか。そういう部分を実はあまり共有できていなかった。スタッフを含めて、以前からチームにいる僕やコーチの佐藤尽さん、2人の言葉の感覚が、あまり伝わり切っていなかった。その後は新しいコーチ陣の助言も入れながら、もう一度自分たちの土台を作り直し、あるいは上積みを作ったりしながら、前半戦の中頃までを進めていきました。
……

Profile
清水 英斗
サッカーライター。1979年生まれ、岐阜県下呂市出身。プレイヤー目線でサッカーを分析する独自の観点が魅力。著書に『サッカーは監督で決まる リーダーたちの統率術』『日本サッカーを強くする観戦力 決定力は誤解されている』『サッカー守備DF&GK練習メニュー 100』など。