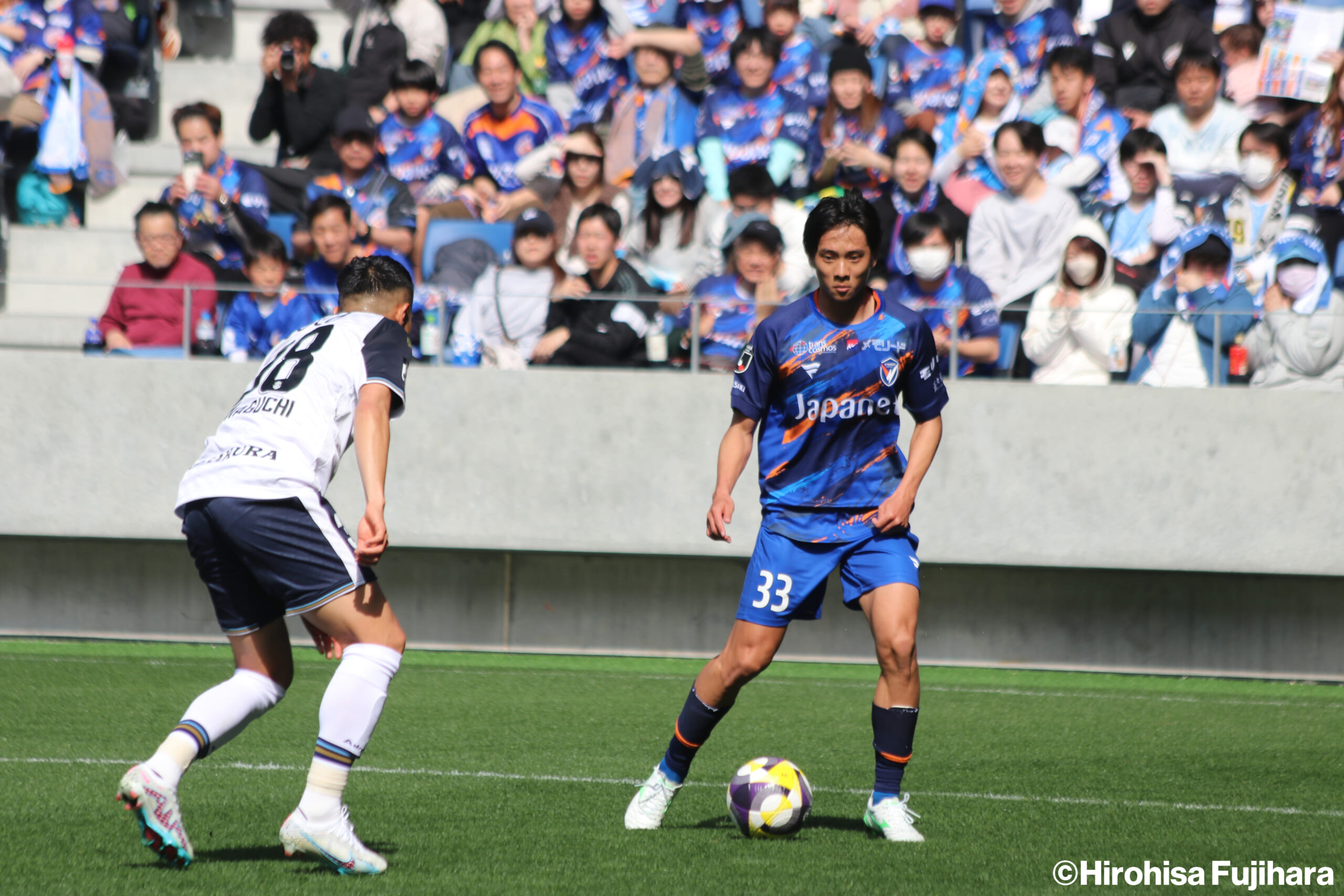遡ること10年前、2014年8月にロコモティフ・モスクワから契約を解除され、1050万ユーロもの損害賠償を請求された上に国際移籍証明書の発行が認められず、11カ月にわたって無所属が続いたラサナ・ディアラ。そこで移籍を妨げたFIFAのルールをめぐって訴訟を起こした結果、今年10月に一部がEU法に違反しているとの判決が欧州司法裁判所から下されたが、この「ディアラ判決」が国際サッカー界を震撼させていることをご存じだろうか?移籍金ビジネスが根本から揺らぐ衝撃と未来を、FIFPRO(国際プロサッカー選手会)アジア支部代表も務める山崎卓也弁護士が前後編に分けて解説する。
移籍金の行方を決める国際労使合意とは?
さて、この判決を踏まえて今後のサッカー界、特に移籍金の仕組みはどうなっていくのか。その鍵を握ることになるのが、移籍金に関する国際的な労使合意が成立するかどうかという点である。
ディアラ判決はFIFAが定めた移籍ルールをEU法違反と判示したものであるが、さらに興味深いのはその判決内容でFIFAはあくまでスイス法に基づいて設立された私的団体にすぎず特段、国家機関から労働条件についての決定を行う権限を与えられているわけではないと判示していることである。これはつまり、選手の転職の自由に関わる移籍金額という労働条件は労使の当事者ではないFIFAが一方的に決めることはできず、労使間での合意が必須であるということを意味している。
実際、移籍金の算定基準について残りの年俸額だけでなく一定の他の要素(例えば選手の年齢)を考慮してより高い金額にするルールにする場合は、それが労使合意という形で行われた場合には例外的にEU法違反でないものとして扱われるというルールが存在する(Albany Exceptionと呼ばれる)。そのため、移籍金を残りの年俸額以上とするルールを作るためには現状では労使合意を行うしかないことになる。
従って今後はWLA(World Leagues Association/世界リーグ協会)とFIFPROなどが中心となって行われる労使交渉で、新しい移籍金の算定基準が合意されるかどうかに注目が集まることになる。もともとWLAとFIFPROは国際マッチカレンダーを一方的に決めるFIFAに対抗する観点から、2022年9月にILO(International Labour Organization/国際労働機構)の仲介の下、国際労使合意(Global Labor Agreement)を締結しており、この移籍金についてもその枠組みで行われることが想定される(なお2022年の時点でWLAとFIFPROはこの枠組みにFIFAを入れて三者合意にすることも提案したが、FIFAはこれを拒否しており、このようなFIFAの姿勢が現在、欧州リーグとFIFPRO欧州支部がFIFAが一方的に導入したクラブW杯を違法として訴訟を提起している背景にもなっている)。
これに対してFIFAはディアラ判決後も自らが引き続き移籍ルールを定める権限を持つ立場であるという姿勢を崩さず、各ステークホルダーに対して今後の移籍規則の修正に関する「意見を募集」する姿勢を示しているが、こうした呼びかけにWLAやFIFPROが応じるとはおよそ考えられず、あくまでFIFAの移籍ルールはWLAやFIFPROとの合意がないと正当化されないという姿勢で臨むことが予想される。
FIFA will open a global dialogue on the transfer system, involving key stakeholders, to adapt article 17 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP).
This announcement follows on from the decision of the Court of Justice of the European Union on the Diarra… pic.twitter.com/T75UOIaYda
— FIFA (@FIFAcom) October 14, 2024
よりビッグクラブ有利という議論は正しくない
では、今後の「労使合意」に含まれるべき、移籍金のルールとはどのようなものであるべきか。
……

Profile
山崎 卓也
1997年の弁護士登録後、2001年にField-R法律事務所を設立し、スポーツ、エンターテインメント業界に関する法務を主な取扱分野として活動。現在、ロンドンを本拠とし、スポーツ仲裁裁判所(CAS)仲裁人 、国際プロサッカー選手会( FIFPRO)アジア支部代表、世界選手会(World Players)理事、日本スポーツ法学会理事、スポーツビジネスアカデミー(SBA)理事、英国スポーツ法サイト『LawInSport』編集委員、フランスのサッカー法サイト『Football Legal』学術委員などを務める。主な著書に『Sports Law in Japan』(Kluwer Law International)など。