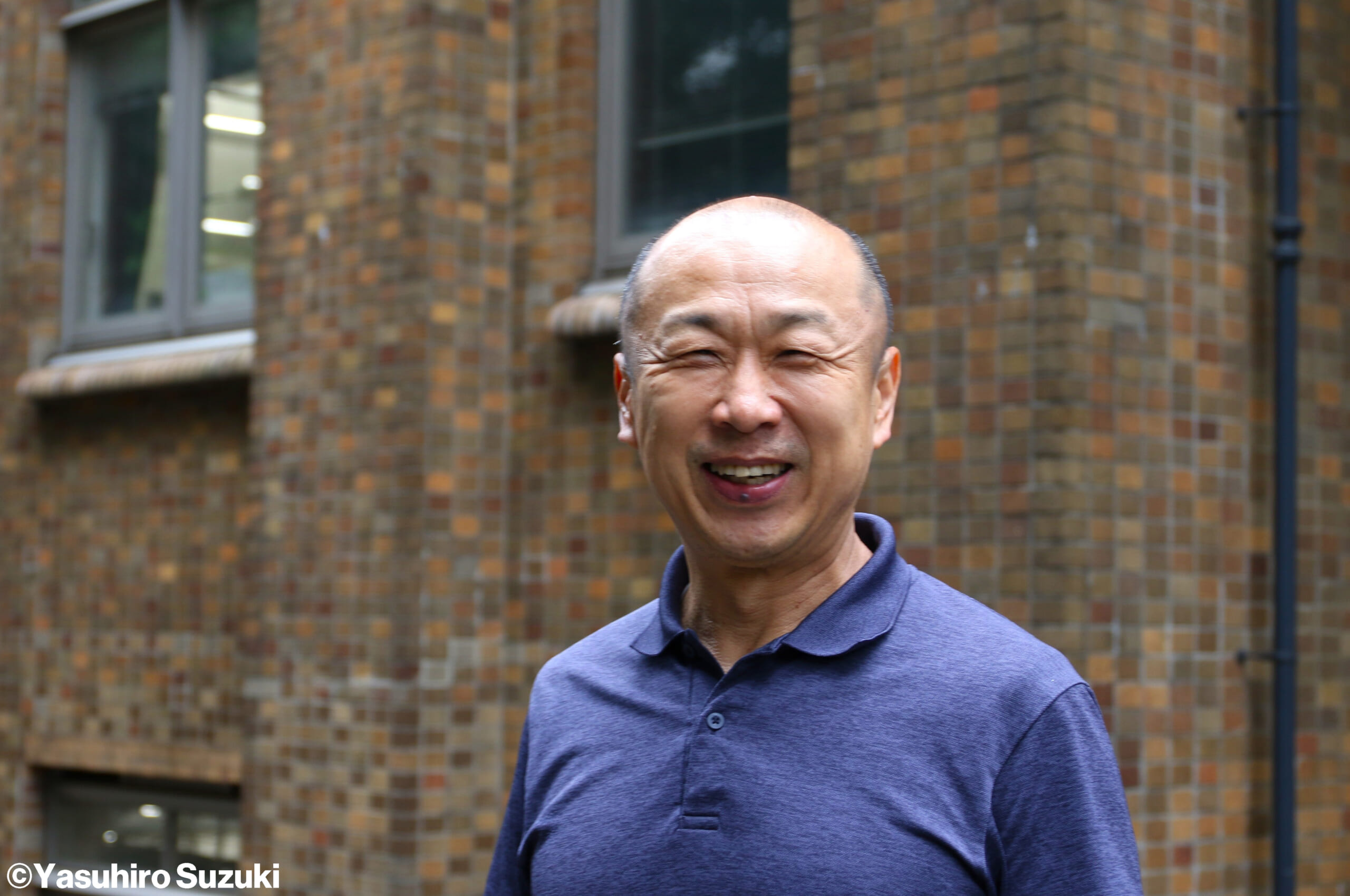決定機は十分。あとは、決めるだけ。長谷川健太体制・初年度に挑む名古屋グランパスの現在地

21試合で16得点。これが現在の名古屋グランパスの、J1における総ゴール数だ。攻撃力アップを掲げてシーズンに入ったものの、いくつもの要因が重なって、チームの得点はリーグ最少と伸び悩んでいる。だが、「決定機は十分つくれている」と主張するのは、普段からチームを観察し続けている今井雄一朗だ。ならば、それを得点へと結びつけるためには、ここから何が必要なのだろうか。その主張の理由と、さらに“その先”を説明してもらおう。
それは単なる“たられば”ではない
勝つためには、と掲げた「攻撃力アップ」のお題目が何とも悩ましい。再現性という言葉がトレンドにも感じられるようになった昨今においても、詰まるところ攻撃は水物である傾向は強い。
100本のシュートも全部外せば0点と言うのはさすがに極端でも、ゴールにボールを蹴り込むのは最終的には一人の選手だ。つまりどこまで行っても決定力とは個の力である。一方で毎試合3本のシュートで3点を取って勝つチームがあったとして、そこに“得点力のあるチーム”というイメージも湧きにくい。さりとて3点取っていれば“少ないチャンスを決めきる”というイメージにもなりにくい。
攻撃力とはできるだけ攻撃の手数を増やし、チャンスの数を増やし、その複数を決め続けるという作業の繰り返しの中で定まってくる評価であり、だからこそ攻撃力アップを目指したシーズンに、名古屋グランパスは苦戦を強いられている。
何しろ、一定以上の決定機はつくれているのだ。リーグ21節終了時点で、手元の集計ではあるが“決定的チャンス”と呼べる場面は得点以外で72回あった。1試合平均で3.4回は決して少なくはない数字だ。
一方でアタッカーポジションの選手がそのチャンスを外した数は48回で、全体の66%にあたる。つまり、ゴール前でチャンスは作れているのに、決められていない。その結果が21試合でのチーム総得点16であり、「50得点はなければ優勝争いはできない」とした長谷川健太監督の指標に対する数字としても、観戦者の見た目を悪くする一つの要因となってしまっている。
「あの決定機を決めていれば」「先制点が取れていれば」とは今季の長谷川監督からたびたび聞かれる言葉だが、それは単なる“たられば”ではなく、それだけの好機を生み出せているからこその、“決まっていれば”という感想や印象、あるいは後悔だと思った方が本音に近いと感じる。

コロナ禍による準備期間の大幅な削減
そもそもの成り立ちを思えば、今季のチームは相当なハンディを背負いながらここまで戦ってきた。新監督を迎えたにもかかわらず、プレシーズンキャンプが新型コロナウイルス感染症によって中断、ほぼ中止という状況に追い込まれたのはその最たるもので、14日間で4試合の練習試合が予定されていた日程は、序盤5日間でストップ。トレーニングマッチ1試合をこなした時点で選手たちはホテル自室での隔離となり、少人数でのグループトレーニングが再開されたのは1週間後のことだった。
チーム戦術の浸透だけでなく、フィジカルコンディションを上げるためにも重要だった期間で、自室待機が1週間もあったことは、シーズンを戦うコンディションづくりにおいて大きく影響があったことは言わずもがな。新チームでの実戦経験もほぼない状態でリーグ開幕を迎えることになったことも、不運としか言いようがなかった。今季の名古屋はキャンプでの沖縄SV戦、そして開幕1週間前に行なったメディア非公開でのジュビロ磐田戦しか練習試合を行えておらず、長谷川監督の「あとはぶっつけ本番というところは否めない」という開幕前日の台詞も純度100%の真実であった。
そうした前置きをした上で、今季の名古屋のチームづくりを追っていくと、いくつかのターニングポイントを数えることができる。当初、長谷川監督は基本布陣[4-2-3-1]の目玉として、前年とは逆の右サイドに相馬勇紀、左サイドにマテウスという配置を考え、彼らの突破力と利き足からの鋭いクロスでゴールチャンス増を目論んでいた。

プレシーズンの練習の中で、強調されていたのはアーリー気味でもいいので、速いクロスをゴール前へ送ること。半ば無理やりにでもゴール前の状況を作り出し、そのフィニッシャーとして新加入の酒井宣福や、1年以上の治療期間を経て調子を取り戻そうとしていた金崎夢生に期待を寄せた。なぜ新指揮官が差し当たってのテーマとしてこのプレーにこだわったかと言えば、就任会見時に語った2021年版の名古屋に以下のような物足りなさを感じていたからだ。
「飛び出してからの得点というのはほぼほぼなかった。本当に、1点か2点くらいで、クロスが多くて、あとはセットプレー。背後へ抜け出す動きはないわけではなく、チームとして共有していない部分があった。動きはあるけど、そこを使わないがためにだんだん止まってきて、どちらかというと外回しのサッカーが多くなってくる。もっとゴールに直結するような動きを使う、そういうゴールを増やしていけば、クロスに非常に長けた選手は何人かいる。昨年の38試合で44得点というのはちょっと寂しすぎる。そこで50点以上取れるチームになってくると、優勝に絡むことができるようになってくる」
就任会見の第一声が「得点力を上げなければいけない」だった監督にとって、チームの武器を活かす術の第一が、DFラインの背後で攻撃を行なうことで、そのための速い展開とゴール前の飛び出しが練習でも強調されてきた。切り替えの速さ、速攻への参加の仕方、守備組織の整備も前体制とは違った決まり事が満載で、だからこそ準備期間が削られたのはこのチームにとって痛恨事でしかなかった。
長谷川健太と西野朗の共通点
迎えたリーグ開幕戦こそヴィッセル神戸の不調にも助けられ、しかも一点集中でトレーニングしてきた速いクロスからの得点(形はオウンゴール)まで生まれたが、以降は4試合勝利できず。チームの練度がどうしても足りない中では看板でもあった“右相馬、左マテウス”の配置を第5節・柏レイソル戦で従来のサイドに戻し、攻撃に何とか改善を求めたのがシーズン最初の変更、マイナーチェンジである。
しかし目先を変える程度の効果しか見込めず、柏戦は引き分けられたものの、次の延期分2節のガンバ大阪、勝った湘南ベルマーレ戦を挟んで迎えた第8節・北海道コンサドーレ札幌との戦いでも、チームには大きな改善が見られなかった。
前述したように、どの試合でも決定機はつくれていたので、それを決めていれば流れとしても変わっていたとは思うが、結果として勝利を挙げられない日々が続く中、現役最多勝監督は大きな決断を下す。微調整ではなく、3バックへのモデルチェンジである。
余談にはなるが、勝っている監督に共通するのは何よりも決断力だ。長谷川監督の3バック変更を見た時、真っ先に思い出したのが2015年1stステージのサンフレッチェ広島戦で、当時の西野朗監督が変更に踏み切った3バックだった。奇策っぷりでは西野監督の方が上で、ウイングバックに永井謙佑を起用する驚きの布陣を、2-0の勝利に結びつけたのだから脱帽である。
応えた永井も相当のものだが、いくら開幕4戦で勝利がなかったとはいえ、永井の能力をウイングバックで使ってしまうこと、公開練習ではまったく見せていなかった[3-4-2-1]の並びを実戦で採用するのは賭けにも近かった。当時のスタッフが「この決断をしてしまうのが西野さんのすごいところなんですよ」よ目を丸くしていたが、翻って2022年、長谷川監督にも同じものを感じたわけである。
札幌に負けた次の試合はルヴァンカップの奇しくも広島とのホームゲーム。リハビリから戻ってきて間もない丸山祐市がスタメンに名を連ねていた時点で我々報道陣の目は丸くなっていたのだが、キックオフしてみるとさらに目を見開かされることになった。
中谷進之介、藤井陽也、丸山による3バックは、それまで守備に曖昧さがぬぐえなかったチームに一つの規律を与え、格段に試合の解像度が上がったことを覚えている。様々な目的で使われる3バックだが、傾向として選手個々の役割や責任をはっきりさせる効能がある。この時期、長谷川監督はしきりに会見で「締まった試合をしたい」と発言していた。組織を構築する時間がなかったシーズンの立ち上がりに対し、結果とのバランスを見れば何かを変えざるを得なかった。
そこでまずは失点を防ぎ、攻撃の土台を築くためにと決断したのが、そのシステム自体に明確さが備わっている3バックである。G大阪で黄金期を築いた名将による、シーズン序盤の広島との試合で繰り出された大胆策。歴史は繰り返すのだと思わされた、シーズン序盤の分岐点である。
藤井陽也、相馬勇紀、森下龍矢。3バック変更で輝いた3人
……

Profile
今井 雄一朗
1979年生まれ、雑誌「ぴあ中部版」編集スポーツ担当を経て2015年にフリーランスに。以来、名古屋グランパスの取材を中心に活動し、タグマ!「赤鯱新報」を中心にグランパスの情報を発信する日々。