「変人」ビエルサこそ一つの理想。サッカー監督の「二面性」を考える
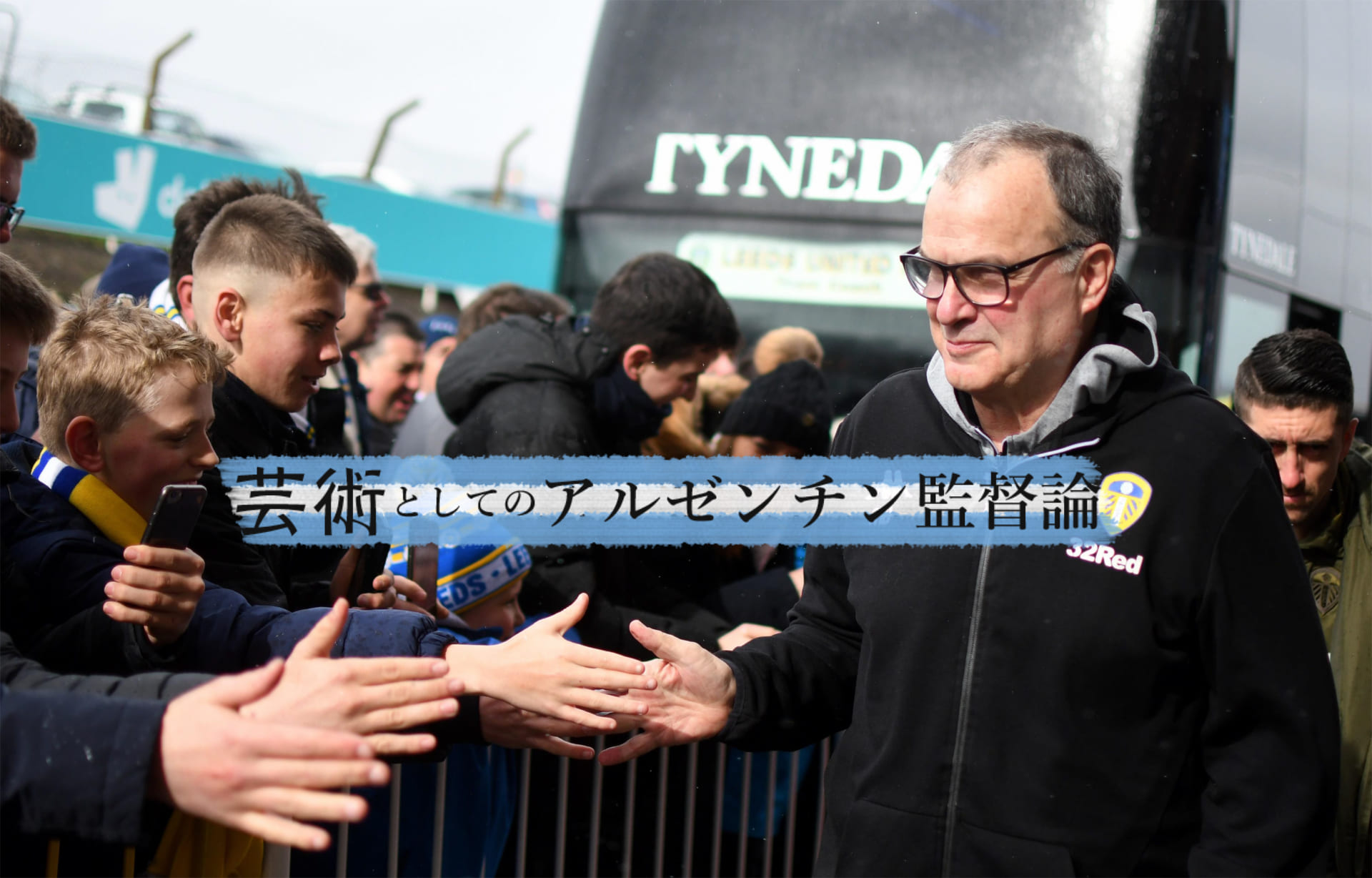
芸術としてのアルゼンチン監督論 Vol.11
2018年早々、一人の日本人の若者がクラウドファンディングで資金を募り、アルゼンチンへと渡った。“科学”と“芸術”がせめぎ合うサッカー大国で監督論を学び、日本サッカーに挑戦状を叩きつける――河内一馬、異国でのドキュメンタリー。
「表と裏」や、「二面性」という言葉が人間に添えられる時、それは大抵良い意味を持たない。「あの人には、表と裏がある」。この言葉を聞いてポジティブな捉え方をする人も、言われてうれしい人もおそらくいないだろう。いわば、悪口の代名詞である。今回は、これまで決して脚光を浴びることのなかった「二面性」という言葉にスポットを当て、この言葉の名誉奪還に一肌脱ぎたいと思う。なぜなら、私は『サッカー監督には二面性が必要である』と確信しているのだから。おそらく日本で唯一「サッカー監督」だけに焦点を当てた連載を書いている身として、この責任をしっかり果たしたいと思う。
ピッチの中と外でまるで「別人」
「良い結果が出なかった時、どんなに良いプロセスであったとしても評価をされないのであれば、それは心配しなくていい。不公平というものは、よく起こるものです。しかし、もしも偶然に結果が出てしまったのであれば、それは皆にとってすごく有害なものとなります。なぜなら、それを見ていたすべての人に、近道こそが目標を達成するには最適な方法だと、そう教えてしまうからです。実際は、そうではありません。これはメノッティ(元アルゼンチン代表監督)の言葉ですが、花壇を避けずに近道をする人は、早くは着きますが花を潰してしまいます。一方で花壇を避けて遠回りをする人は、時間はかかりますが花をダメにすることがありません。私はこのような言葉を信じています。根拠のある結果こそ、評価されるべきだと信じているのです」
これは、アルゼンチンを代表するサッカー監督マルセロ・ビエルサの言葉だ。彼が選手の前で、また記者の前で話をする時は、まるで思想家のような、また哲学者のような姿を見せるのが常である。子供のファンを見た時は顔をくしゃっとさせ、満面の笑みで頭を撫でる。記者会見や講義でサッカーの説明をする時は、研究者や学者のように、資料を見せながら冷静に言葉を並べる。しかし、それらの姿を見ているだけでは、彼の本質を知ることはできない。練習中のグラウンドで身体全体を使い、文字通り声という声を絞り出して選手を動かす姿、試合中のベンチで選手や相手や審判に対して怒り狂う姿も、それらはすべてマルセロ・ビエルサという一人の人間であり、一人のサッカー監督である。私はこれを、サッカー監督が持ち合わせていなければならない「二面性」であると、そう考えてきた。
良いリーダーとは、なにか? それをここで定義するつもりはない。決して1つではないだろう。しかし、サッカー監督というリーダーにおいて絶対に欠けてはいけないものがあるとすれば何か? と聞かれれば、“私は”「二面性である」と、そう答える。その「一面」ともう「一面」は、「静と動の差」もしくは「理と情の差」と言い換えることもできるだろうか。
世界中にいる「優秀な監督」に、この「二面性」を持ち合わせていない例を見ることは出来ない。お行儀が良さそうな、お淑やかそうな、上品な監督を思い浮かべると、例えばイタリア人のカルロ・アンチェロッティが浮かんでくるだろう。彼も当然「二面性」を持ち合わせている。試合中のベンチで怒り狂う姿があれば、メディアに対して冗談を言う、人柄の良さそうな姿もある。いつも謙虚で、「若い優等生」のイメージが強いドイツ人監督ユリアン・ナーゲルスマンは、ベンチに向かって投げたペットボトルが、観客の1人に当たってしまったことがある。そのあと、すぐに優等生らしく観客席に謝りに行ったその姿と、ペットボトルを投げた時の狂気的な表情を、「二面性」と表さずにどう表現すれば良いと言うのだろうか。聖人のようにインタビューに答えるペップ・グアルディオラと、アーセン・ベンゲルを罵倒するペップ・グアルディオラは、別の人だろうか。同じ人である。

私がサッカーを愛している理由、もしくは、評論家ではなくプレーヤーでいたい理由は、ピッチの上では、なぜか、そうなぜか、感情を抑えることができないからである。日常生活で誰かに怒りを表明したり、誰かを投げ倒したりした記憶は、まったくない。誕生日を祝われるのが最も苦手だ。うれしいのにリアクションがうまく取れないからである。つまり、生活の中で感情を沈静させることは、容易も容易なのだ。それなのに、ピッチの上では、練習中も、試合中も、どうしてもそうはいかない。選手の時も指導者になってからも、怒りを表明し、喜びを爆発させずにはいられないのだ。私は、サッカーをすることによって唯一、自分の「二面性」を見て取ることができる。自分では制御できないほどの「なにか」を、自分に見せてくれる唯一のものが、私にとってはサッカーなのだ。
ジョゼ・モウリーニョがピッチから離れてしばらく経った今、インタビューに答えるその姿は穏やかで、「戦場」に立つ彼とはまるで別人のようである。その姿を見ると、私たちサッカーを愛している人間は、監督、選手、ファン問わず、サッカーをやっていなかったら出てくるはずのない自らの「二面性」に、言葉にできない何かを感じているのかもしれない。その汚くて美しいサッカーを作り出す「監督」という人間には、どうしても譲れない「なにか」が、なくてはならないのだ。

「怒る=悪」ではない
「怒る」という行為に対して、日本では「=してはいけないこと」のような認識があるように思う。それは「怒る」という行為を、「教育」とやらのために「都合の良い裏技」として使ってきた、愚かな大人たちの責任である。私がこの記事で書いてきたものは、「怒る」という言葉よりも「情熱の表明」と呼ぶのがふさわしいのかもしれない。私は決して、それが悪いことだとは思わない。サッカーというスポーツにとって、大事な、それはそれは大事な要素である。「都合の良い裏技」と一緒にしてはならないのだ。
「喜ぶ」という行為が時に批判されてしまうのも、子供たちがそれを表明できないのも、それをサッカーにおいて制圧してきた大人たちの責任である。私が記事の中で、あえて「表と裏」ではなく「二面性」という言葉を使っているのは、それがどちらも「面(おもて)」であるからだ。確かに、リーダーに「表と裏」があってはならないのかもしれない。しかし、自らが持つ「面(おもて)」を正直に見せることは、サッカー監督にとって、リーダーにとって、いや人間にとって、大切なことなのかもしれない。
最後に、ビエルサがメノッティの言葉を引用したように、私も日本人として、松下幸之助の言葉を引用して、この記事を締めたいと思う。
「理を追求して、情を添える」
理屈や理論を追求できないリーダーも、そこに感情を添えることができないリーダーも、どちらも話にならないのである。
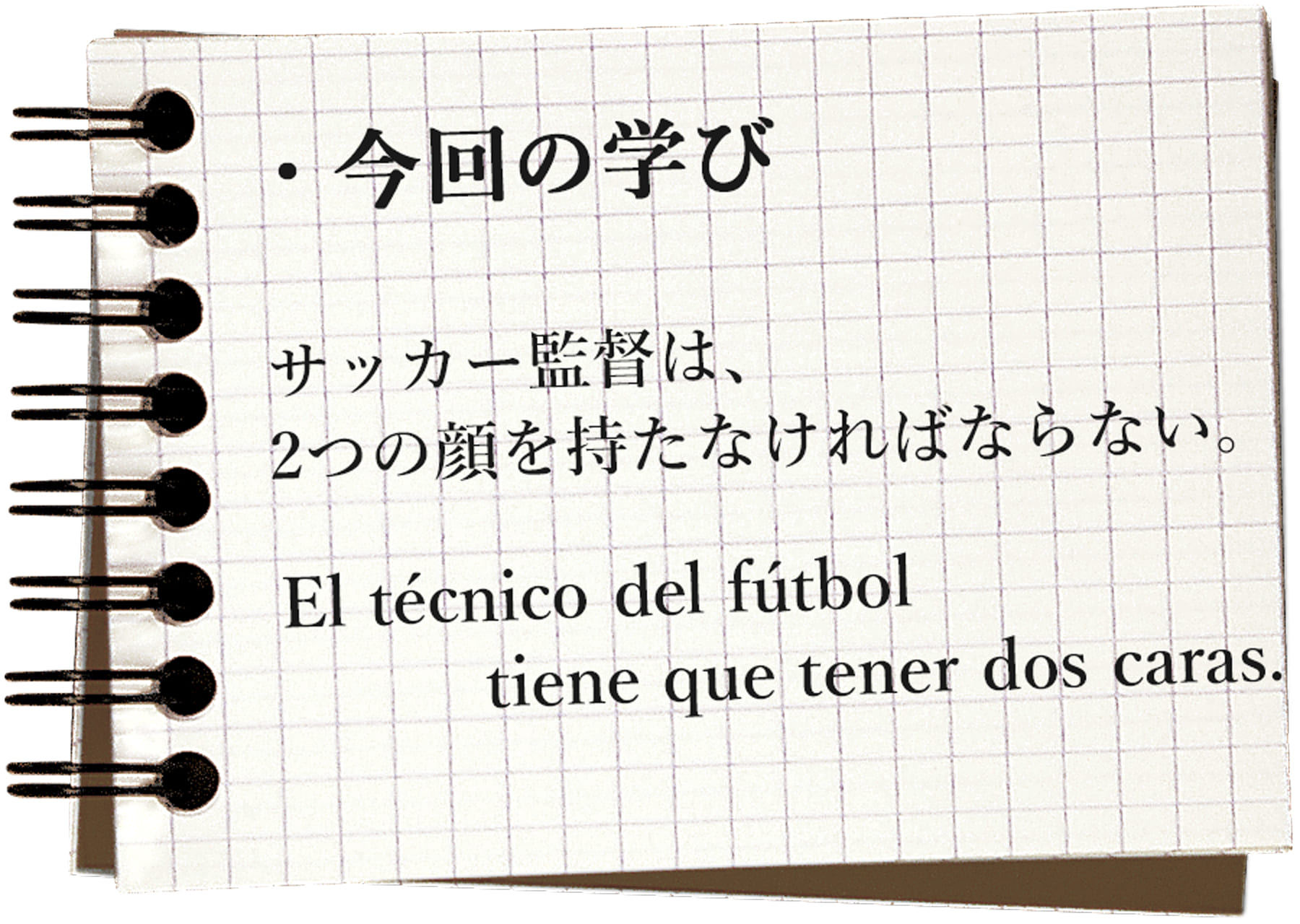
芸術としてのアルゼンチン監督論
- 【Vol.1】アルゼンチン人監督の謎解きの旅。ビエルサに魅せられて監督学校へ
- 【Vol.2】「サッカーで年は関係ない」の意味。アルゼンチン指導者を育む議論文化
- 【Vol.3】アルゼンチンの「カオス」に学べ。異なるバックボーンが何かを生む
- 【Vol.4】サッカー監督に求められるのは「対話」ではなく「演説」の力
- 【Vol.5】アルゼンチンの監督学校で習った伝える力――教授法の3つの要素
- 【Vol.6】揺れる伝統国、アルゼンチンの育成論。サッカーの天才は「作れる」のか?
- 【Vol.7】ポチェッティーノは慌てない。「臨機応変に対応する力」の源泉
- 【Vol.8】サッカーをする子供たちの目的は? 哲学するアルゼンチンの指導者たち
- 【Vol.9】現役監督G.ミリートの講義で思う「サッカー監督=ツアーガイド」説
- 【Vol.10】ここがヘンだよ、アルゼンチン人。“外国人の視点”で弱点を探る
- 【Vol.11】「変人」ビエルサこそ一つの理想。サッカー監督の「二面性」を考える
- 【Vol.12】アルゼンチンに来た若者が感じた優秀なサッカー監督を生む理由
Photos : Getty Images

Profile
河内 一馬
1992年生まれ、東京都出身。18歳で選手としてのキャリアを終えたのち指導者の道へ。国内でのコーチ経験を経て、23歳の時にアジアとヨーロッパ約15カ国を回りサッカーを視察。その後25歳でアルゼンチンに渡り、現地の監督養成学校に3年間在学、CONMEBOL PRO(南米サッカー連盟最高位)ライセンスを取得。帰国後は鎌倉インターナショナルFCの監督に就任し、同クラブではブランディング責任者も務めている。その他、執筆やNPO法人 love.fútbol Japanで理事を務めるなど、サッカーを軸に多岐にわたる活動を行っている。著書に『競争闘争理論 サッカーは「競う」べきか「闘う」べきか』。鍼灸師国家資格保持。














