サッカーをする子供たちの目的は?哲学するアルゼンチンの指導者たち

芸術としてのアルゼンチン監督論 Vol.8
2018年早々、一人の日本人の若者がクラウドファンディングで資金を募り、アルゼンチンへと渡った。“科学”と“芸術”がせめぎ合うサッカー大国で監督論を学び、日本サッカーに挑戦状を叩きつける――河内一馬、異国でのドキュメンタリー。
私が今関わっているクラブには、トップチームからシニアチーム、小さな子供に至るまで、びっくりするくらい多くの選手たちが所属している。ある一人の指導者に聞いた時は「子供たちだけで300人はいる」と言っていたが、私の見ている印象ではそれよりもさらに多い気がしている。育成のカテゴリーでは、20人前後の選手たちに対して3人ほどのコーチがついていて、その他に1人のフィジカルコーチが帯同するわけであるから、選手たちの人数に伴って当然指導者も大量にいることになる。
その指導者たちに向けて、このクラブでは月に数回講習会のようなものを実施しているという。私が初めてそれに参加した時のテーマは『サッカーにおけるコーチングと神経科学 ~脳をトレーニングすることは可能か?~』であった。「Neurociencia(直訳:神経科学)」と呼ばれている分野は、私が通っている指導者養成学校でも長い時間をかけて扱われていて、アルゼンチンという国がサッカーというスポーツにおいて非常に重要視している部分だということがわかる。女性の講師が、事前に作成されたスライドを用いながら軽快に話を進めていく。この国の人々は本当に人前で話すのが上手だ、という話は以前この連載の中でも書いたように思う。講義の内容自体は過去に授業で触れていたようなことで、特別興味深いものはなかったが、それ以上に私が印象に残っているのは講義を受ける指導者たちだった。
■突然、講義を中断しての大激論
講義が始まって1時間半ほどが経過した時、話は「モチベーション」を中心に展開され始めていた。モチベーションの種類や役割、なぜ私たちサッカーの指導者がモチベーションについて学ばなければならないのか、などの話の中で、モチベーションを保つためには何らかの「目的」が必要である、という至極当然とも言える点を講師が述べたとことで、講義を中断せざるを得ない状況になった。それは、彼らが「目的」という言葉に引っかかってしまったからだ。「サッカーをする子供たちの目的って、何だ?」。ここから、息をつく間もないほどに討論が始まった。
日本では、「哲学」という言葉が少し煙たがられているような印象がある。もちろん私も例外ではなく、興味を持ちながらも「自分なんかが……」とずっと思ってきた青年期だった。私たちが印象づけられている「哲学」とは、ある一つの難解な学問であり、「研究」としての意味合いが強い。それゆえ私たちは、「哲学する」という言葉の意味を理解しづらいのではないだろうか。少なくとも私の人生では、学校で「哲学する」機会を与えられた記憶はあまりない。本来「哲学」とは万人に必要なものであるにもかかわらず、一部の人の「研究」の対象としてのみ意味を持つようになってしまうのは、日本の現状と言わざるを得ないのかもしれない。哲学者の鷲田清一氏は、自身の著書『濃霧の中の方向感覚』の中で、西洋の哲学事情について、こう書いている。
“手許にあるフランスの教科書を開けてみると、たとえば「よくものが見えているというのは幸福への障碍になるか」とか「もっともよい統治とはもっとも少なく統治することか」とか「歴史家に必要なのは記憶だけか」といった問いと並んで、「芸術作品が商業取引の対象となるのは正しいことなのか」といった問いもある。こんなことを高校生が授業で議論しているのである”
実際のところ、私は昨今における海外の哲学事情に詳しいわけではないが、これまで読んできた教育者や哲学者が書いた本の数々によれば、海の外では学校教育において「哲学する」ことが非常に重要視されているようである。もちろんこれについて「海外が良くて日本が良くない」と言うつもりは毛頭ないが、日本の教育のように「答え」(だと大人が決めていること)を暗記する教育に慣れてきた私には、地球の反対側で目撃している異常なまでの「議論」の様子に、驚きを隠さずにはいられないのだ。鷲田清一氏は同著の中で、「哲学する」ことをこう表現している。
“「自分たちの問題をいつもよりちょっと過剰に考えたい」(戸田山和久)という人たちが集まれば、そこに「哲学する」ことが立ち上がる。「哲学する」とは、知っている(と思い込んでいる)ことを改めて問いなおす作業だ。”
私が講義室で目撃したのは、間違いなくアルゼンチン人のサッカー指導者たちが「哲学する」姿であった。彼らにそのことを話せば「そんな難しいこと言うなよ」と笑われるかもしれないが、西洋をルーツに持つ彼らは自然と「哲学している」ように私には見える。「子供たちは週末に勝つことが目的なのか?」「それともプロになること?」「それなら僕らのようなアマチュアクラブとプロクラブにいるエリートたちは目的が違うのだろうか?」「中には試合でゴールを決めることだけを目的としている子だっているけど、それは間違いなのか?」「コーチの目的と子供たちの目的は異なるのか?」などの問いとともに、「私はこう思う」と誰もが当たり前のように主張する。その日は講義内容を継続するのを辞め(辞めざるを得ず)、時間が来るまでこれについての発言が止まることはなかった。
■「答えのない問い」を考え続ける日常
もしかすると日本人は、このような「答えのない問い」であればあるほど、黙り込んでしまうかもしれないし、元から計画された講義内容を継続することを優先して、「哲学する」のを中断させてしまうかもしれない。今思うと、私が大学チームで指揮を執っていた時、「大学生がサッカーをする目的は何だ?」と一人悩んだ。それがはっきりしなければ、彼らのモチベーションを上げることも、モチベーションを保つことも、寄り添うことも厳しくすることも、何もかもが「ズレて」しまうことはわかっていたからだ。ただ私は、それを選手たちと共有せず、議論せず、一人で悩み、一人で答えを出した(つもりになった)のだった。それを今では、すごく後悔している。そんな指導者が、良い指導者のわけがない。
サッカーというスポーツでは、この「哲学する」という姿勢が、私たちが考えているよりもはるかに重要な意味を持っているのではないだろうか。答えのない世の中を問うて生きるのと同じように、決して一つの答えがないサッカーに対して「しつこく考える」ことから逃げず、永遠と議論することに対しての忍耐力を鍛え、そのための時間を惜しんではいけないのではないだろうか。「哲学」とは、難しい本を読むことではなく、わかっていると思っていることについて、いつもより過剰に議論を重ねる姿勢のことなのだ。その姿勢は、ますます複雑な問題に否が応でもぶつかるサッカー界を生きる者たちにとって、なくてはならない姿勢なのかもしれない。その文化を自然に持ち合わせているのが西洋人なのであれば、彼らがサッカーという競技で先を行く理由も、この競技を発展させている理由も、わからなくはない。
チームという「社会」に「哲学する」姿勢をもたらすことができるのは、他でもなく、指導者であり、監督である。
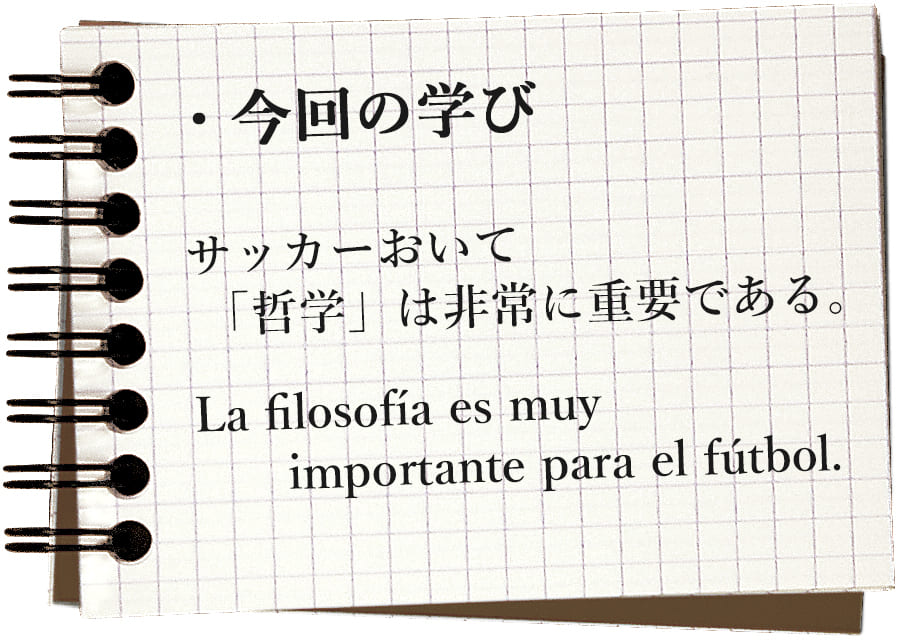
芸術としてのアルゼンチン監督論
- 【Vol.1】アルゼンチン人監督の謎解きの旅。ビエルサに魅せられて監督学校へ
- 【Vol.2】「サッカーで年は関係ない」の意味。アルゼンチン指導者を育む議論文化
- 【Vol.3】アルゼンチンの「カオス」に学べ。異なるバックボーンが何かを生む
- 【Vol.4】サッカー監督に求められるのは「対話」ではなく「演説」の力
- 【Vol.5】アルゼンチンの監督学校で習った伝える力――教授法の3つの要素
- 【Vol.6】揺れる伝統国、アルゼンチンの育成論。サッカーの天才は「作れる」のか?
- 【Vol.7】ポチェッティーノは慌てない。「臨機応変に対応する力」の源泉
- 【Vol.8】サッカーをする子供たちの目的は? 哲学するアルゼンチンの指導者たち
- 【Vol.9】現役監督G.ミリートの講義で思う「サッカー監督=ツアーガイド」説
- 【Vol.10】ここがヘンだよ、アルゼンチン人。“外国人の視点”で弱点を探る
- 【Vol.11】「変人」ビエルサこそ一つの理想。サッカー監督の「二面性」を考える
- 【Vol.12】アルゼンチンに来た若者が感じた優秀なサッカー監督を生む理由
Photo by Musiena on Reshot

Profile
河内 一馬
1992年生まれ、東京都出身。18歳で選手としてのキャリアを終えたのち指導者の道へ。国内でのコーチ経験を経て、23歳の時にアジアとヨーロッパ約15カ国を回りサッカーを視察。その後25歳でアルゼンチンに渡り、現地の監督養成学校に3年間在学、CONMEBOL PRO(南米サッカー連盟最高位)ライセンスを取得。帰国後は鎌倉インターナショナルFCの監督に就任し、同クラブではブランディング責任者も務めている。その他、執筆やNPO法人 love.fútbol Japanで理事を務めるなど、サッカーを軸に多岐にわたる活動を行っている。著書に『競争闘争理論 サッカーは「競う」べきか「闘う」べきか』。鍼灸師国家資格保持。














