必然のギャンブル?ポーランド戦、日本はなぜ機能しなかったのか?

林舞輝の日本代表テクニカルレポート第3回:日本対ポーランド
欧州サッカーの指導者養成機関の最高峰の一つであるポルト大学大学院に在籍しつつ、ポルトガル1部のボアビスタU-22でコーチを務める新進気鋭の23歳、林舞輝が日本代表のゲームを戦術的な視点から斬る。第3回のテーマは、今でも議論が二分している「談合サッカー」ではなく、「ポーランド戦の日本はなぜ機能しなかったのか?」を検証する。
試合時間、残り10分。西野監督は長谷部を投入し、このまま0-1の負けで終わらせコロンビアの守備力に運命を託すという鳥肌の立つような決断をする。
通常「談合サッカー」は両者とも他会場の結果は関係なしに引き分けで終われば突破できる場合などで行われるが、今回はセネガルが残り10分で1点でも決めれば一瞬で敗退が決まるというリスクのある「談合サッカー」だった。肝が据わっていると言えばそうなのだが、完全に他力本願の無気力サッカーと言われても否定はできない。自力で突破する可能性がありながら、運命を他会場に託した。この最後の10分の博打についてはすでに多方向で様々な意見が散見されたが、一言で言ってしまえばこれはスポーツ、もしくはサッカーへの価値観の問題だ。ある意味でただの賭けであり、そこに正解はない。だからこそ、ここまで様々な意見・考えが飛び交ったのだろう。
だが、この試合の真の問題はそこではない。私は賭けの話をするつもりはないし、他人の価値観にとやかく言うつもりはない。なぜなら、「博打」や「賭け」に出なければならないという状況になった時点で、それはつまりサッカーというゲームへの攻略失敗を意味しているからだ。私たちが今すべきなのは正解のない賭けの話ではなく、不正解だったポーランド戦というゲームの話だ。
初めから破綻していたメンバー構成
日本は序盤からポーランドにボールを持たせてミドルゾーンまである程度引き、裏のスペースを残した状態で相手のビルドアップからボールを奪ってカウンター、という形を狙っていた。ポーランドのCB2人があまりビルドアップに長けていないこととスピードがないことを考慮すると、持たせてカウンターという戦術とそのための前線でコースを限定し追い込むためのプレスがうまい岡崎&武藤の2トップの構成は、一見合理的に思える。が、このプランには少し疑問が残る。なぜなら、すでに敗退が決まっているポーランドが積極的にボールを保持し攻めてくる保証はなかったからだ。
例えば、2010年南アフリカW杯グループステージ最終戦のデンマーク戦(3-1で日本が勝利)のように、日本は引き分けでオッケーで相手のデンマークは勝たなければならない、というようなシチュエーションでならこの戦術を採るのは理解できる。相手はリスクをかけてボールを保持し攻撃しなければならない。が、今回は数字上何も背負っていないポーランドだ。積極的に攻めてくるとは限らないし、実際リスクをかけて前に出てくる理由はあまりなかった。もちろん、プライドを懸けて攻勢に出てくるかもしれないが、それは誰にもわからない。その時点でギャンブルであり、有効な策であったかは疑問だ。罠を仕掛けてもかからない可能性は大いにあった。
この試合、日本は先発を6人入れ替え、[4-4-2]を採用。突然この布陣を使った意図だが、おそらく、カウンターのためにポーランドの[4-4-2]にそのまま噛み合わせて当てにきたということなのだろう。猛暑と中3日いうコンディションの中、フレッシュな選手を使い前の試合でプレーした主力を何人か休ませることを選んだ。
だが、メンバー構成のバランスは非常に悪かった。悪いというか、どうしても矛盾してしまう。例えば、右サイドMFに本職でない酒井高徳を入れた理由をポーランドの強力なサイドアタックを封じるためだと解釈すると、左サイドに守備力がない宇佐美を使ったのと整合性が取れない。実際、左サイドから大きなチャンスを何度か作られていた。また、相手のサイドアタックはある程度は封じることに成功するも、自チームへのカウンター機能の実装には失敗した。例えば、カウンターを採用するならば、スピードのあるアタッカーが必要だが、日本の前線にカウンターで能力を発揮できるようなスピードのあるアタッカーはいなかった。右サイドMFに酒井高徳を使った時点で右からの攻撃は捨てているし、左の宇佐美もカウンター型の選手ではない。主力を休ませたかったのが大前提であろうが、端的に言えば、「23人のメンバー選考を間違えました」と認めているようなスタメンであった。

「攻守のデザイン」がまったくない
また、「相手CBのビルドアップ能力の欠如につけ込んで、わざと相手にボールを持たせCBのミスからカウンターを狙う」以外に、攻めも守りも明確なデザインがなかったのは、この試合の一番の問題であろう。
相手のビルドアップ以降の段階ではどうやって守るのか、こちらがポゼッションを保持しポーランドがある程度引いた場合はどうやって攻めるのかなど、そのデザインやプランはまったくと言っていいほど見られなかった。守備では柴崎と山口の中盤2枚のバランスが悪く、2人ともボールに食いついてポジションを守れず、背後や真ん中のエリアを楽々と奪われるシーンが何度もあった。特にポーランドが右サイドMFと左サイドMFを入れ替えてからは、右サイド内側にポジションを取るクルザワに翻弄され左サイドを崩されて危険なクロスを許すシーンがあった。
攻撃でも、柴崎にビルドアップのすべてを託し、崩しは宇佐美の打開力にすべてを賭ける以外の策が見当たらなかった。そして、柴崎にボールが渡らなければ何も始まらず、宇佐美は結局ほとんど個で打開できなかったため、ポゼッション攻撃では窒息状態になってしまっていた。右サイドでサイドMFの酒井高徳が中に入り空いた外のスペースを酒井宏樹がドリブルで運んで行ってアーリークロスという攻撃シーンもあったが、あれもデザインされていたというよりも、酒井高徳が中に入ってボールを失う場面が何度もあったために酒井宏樹にはそれしか手段がなかったという方が正しいだろう。
相手に持たせてカウンターしか策がない日本と、動きはなく攻める気も守る気もあるのかないのかよくわからないようなポーランド、という、W杯全試合の中で今のところ最も迫力のない前半であった。

深さを取る2トップ、ライン間は無人…
後半の初めに、岡崎がケガにより大迫と交代。ここでも、大迫と武藤の2トップがあまりうまく機能しなかった。守備面では、それまでポーランドのビルドアップの中心クリホビアクをうまく切りながらプレスをしていた岡崎がいなくなり、ビルドアップの阻害があまりできず。攻撃面では、今まで1トップで自由に動き回れた大迫にとってあまり一緒にプレーしたことがない選手との2トップはやりにくそうに見えた。そして、それ以上に2人がどちらも深さを取るような選手であることに問題があった。方法は違えども両選手とも深さを取るタイプのFWなので、深さは取れるもののDFとMFのライン間のスペースを使えない。これによって日本のポゼッション攻撃は完全に窒息する。前半は岡崎が引いてボールを引き出し有効に使っていた。失点後に乾が入り、乾が外から中に入ってこのライン間で積極的に受けようとし始め、それにより再度チャンスが作れるようになるのだが、このライン間のスペースを最初からもっと利用するべきだったように思える。
ポーランドはW杯以前からDFとMFのライン間に入って来る選手の対応に組織として大きな問題があり、これはポゼッション攻撃をする上で最も有効に突ける弱点であったし(そのためフットボリスタ本誌で私は香川の“偽9番”を提唱していた)、この試合では(ポーランドのモチベーションの低下もあり)その弱点が非常に顕著であったにもかかわらず、有効にこのライン間のスペースを使えなかった。ライン間攻略は、本来日本の強力なストロングポイントだっただけに、なおさらもったいなかった。
日本の守備面では、相変わらず中盤の2人がボールに寄り過ぎたり容易にサイドに食いつかされたり、ポーランドが何か工夫をしているわけでもないのに中盤がガラ空きになるという、このレベルではあり得ないシーンが何度もあった。また、ボール保持時はほとんど何もデザインされてないことから、ポジショニングもボールの奪われ方もその後のリアクションも悪く、引き分けでグループ突破が決まるのでリスクをかけて攻める必要のないはずの日本がまともにカウンターを受けるという摩訶不思議な状況が頻発した。
失点シーンも、日本は前の2試合からセットプレーの守備で大外の選手を外す傾向があり、そこを見事に突かれた形だ。キッカーが助走した瞬間に一番大外を遅れて後ろから入って来るクリホビアクが見え、その瞬間に「やられた」と確信した。結局その選手に注意が向いて対応しようとした日本の選手が真ん中を空けてしまい、ベドナレクがほぼフリーとなりゴール。セットプレーの守備でのマークの付き方や守り方の修正は必須だろう。

実は博打ではない。最後だけは誤魔化さなかった
試合を総括すると、設計図も地図もない何もデザインされていないサッカーで誤魔化し誤魔化しやりながら、最後も他会場に結果を委ねるという博打で何とか決勝トーナメント進出を決めた。
その誤魔化し誤魔化しで進んでいった試合の中で、最後の10分での西野監督の決断は称賛されるべきものであるし、監督として最大のリスペクトに値するものだ。少なくとも、彼は「覚悟を決めた」のである。長谷部投入も含め、その決断は決して誤魔化さなかった。他力本願であろうと、失敗した時にすべてを失うリスクがあろうと、彼は覚悟を決めた。そして、実はこの決断は世間で騒がれているほどの博打でもないことも確かだ。最後の10分で日本があやふやなサッカーのままで得点する可能性と、カウンターから失点する可能性と、コロンビアがセネガル相手に失点する可能性を天秤にかけた。その結果、攻めには行かず他会場のコロンビアの守備力に運命を委ねるのが最も可能性が高いという結論に達した。ただ、それだけのことである。

もしコロンビア対セネガルが80分時点で同点であり、コロンビアが残り10分で得点することを信じて談合サッカーを敢行したら、確かにそれは世紀の大博打である。そう考えると、今回、実はそんなに可能性の低いものに賭けたわけではない。
これについて筆者の率直な意見を言わせてもらえば(これは完全に自分のサッカーへの価値観である)、これがサッカーだということを日本中に知らしめることができた良い機会であったように思う。「あんなサッカーは子供たちに見せられない」などの意見があるのも知ったが、ならば絶対に見せるべきだ。残念ながら、これこそがサッカーだからだ。夢をぶち壊して申し訳ないが、大抵サッカーは美しくないし、清くもないし、正義も夢もない。道徳的な行いが報われるとは限らないし、倫理観など皆無のプレーが往々にして報われることがある。西野監督本人の言葉を借りれば、「不本意な決断」を強いられることもある。結果が見えない状態ですべてを一気に失うリスクも覚悟し、勝つために自分の信条にそぐわない決断をブーイングを浴びせられながら行わなければならない。これが現実だ。そういうギリギリの世界なのだ。これが現実のサッカーであり、これこそ現実の日本サッカーだ。「子供たちに夢を与える」「子供たちが目をキラキラさせる」、それがサッカーだと思ったら大きな間違いである。子供たちが勘違いしないためにも、これがサッカーであるということを知らせるべきだし、何よりも自力で突破を決めに行くよりコロンビアの守備力に運命を託した方が可能性が高いという日本のサッカーの現実を、私たちはもっと理解しなければならない。まるで日本が強いかのような夢物語を信じ、自力で突破を決められるという錯覚を抱き、サッカーは素晴らしく美しいフェアなスポーツだと偽りのファンタジーを夢見るのではなく、このスポーツで生き抜くには汚さやずる賢さ、相手を出し抜く狡猾さ、そして今回のようなスポーツマンシップやフェアさや正義の欠片もないプレーをしなければならないことを知り、それを受け入れなければならない。でなければ、この世界では生き抜けないだろう。残念なことに、サッカーは日本のスポーツではない。礼も儀もない。狐を相手にする時は狐の発想で立ち向かわなければならないのだ。もしそれができないならば、どんな相手よりもはるかに強くなるしかない。
Photos: Getty Images
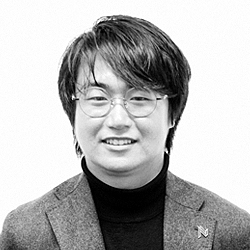
Profile
林 舞輝
1994年12月11日生まれ。イギリスの大学でスポーツ科学を専攻し、首席で卒業。在学中、チャールトンのアカデミー(U-10)とスクールでコーチ。2017年よりポルト大学スポーツ学部の大学院に進学。同時にポルトガル1部リーグに所属するボアビスタのBチームのアシスタントコーチを務める。モウリーニョが責任者・講師を務める指導者養成コースで学び、わずか23歳でJFLに所属する奈良クラブのGMに就任。2020年より同クラブの監督を務める。









