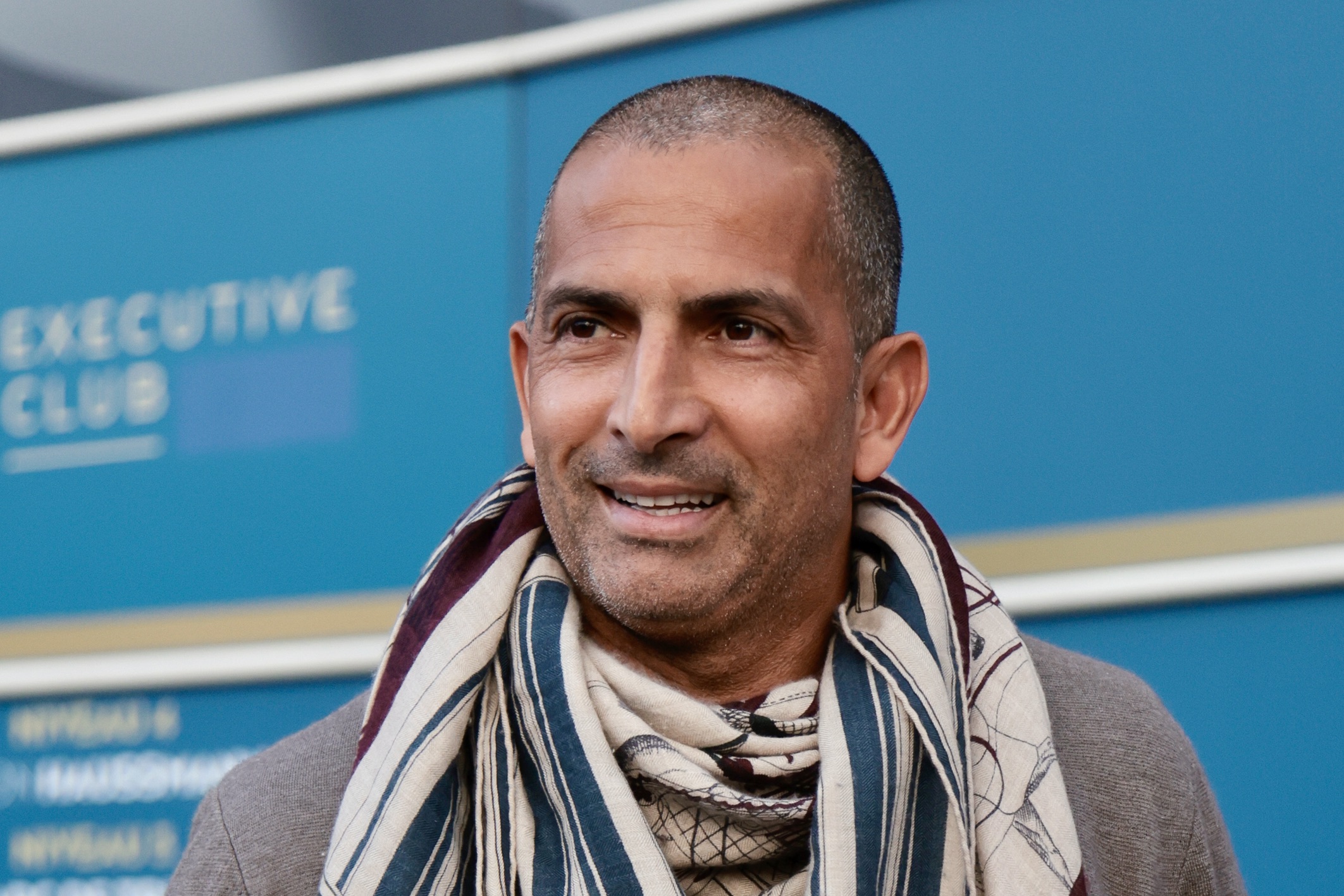なぜ日本サッカーにマルチスポーツが必要なのか?(後編):クラス替えから学ぶ、ウェルビーイングと自己決定理論の本質

近年、日本サッカー界でもよく見聞きする「マルチスポーツ」という言葉。「子供たちが複数のスポーツを同時期に行うこと」の利点としては競技力向上が強調されがちだが、実はリーダーシップの習得やウェルビーイングの向上など、スポーツの社会的価値そのものを引き上げていく可能性も秘めていることをご存知だろうか?その専門家でスポーツ庁から「地域における子供たちの多様なスポーツ機会創出支援事業」の委託を受ける筑波大学体育系教授・大山高氏に、前後編に分けて話を聞いた。
マルチスポーツとウェルビーイングを繋ぐ自己決定理論とは?
――その他にも興味深いマルチスポーツの研究があれば教えてください。
「今、マルチスポーツの研究ではウェルビーイングとの関係性が注目されていて、例えばニュージーランドでは3〜5つのスポーツを経験した子供の方が1や2つに専念した子供と6つ以上(やりすぎ)の子供よりも、OECD(経済協力開発機構)の基準を用いたウェルビーイングの得点が高いことが明らかになっていて、国際誌にも取り上げられています」
――「ウェルビーイング」とは何でしょうか?
「ウェルビーイングは身体的、精神的、社会的に満たされている状態を指しています。今は誰一人取り残さない社会のための17の目標としてSDGsが掲げられているんですけど、実は2030年までの未来しか考えられていないんです。そこで次はSWGsというみんなで持続可能なウェルビーイングを目指す目標を設定していく動きもあるくらい、国際的に注目されている価値観ですね。SWGsというみんなで持続可能なウェルビーイングを目指す目標も登場していて、量的な豊かさを測るGDP(国内総生産)だけでは捉えきれない、文化的な多様性も考慮した指標としてウェルビーイングも国の競争力の目安に組み込まれていく見込みです」
――その向上にマルチスポーツがどのように役立っているのでしょう?
「ウェルビーイングを高める上では、自己決定理論に基づくバランスが重視されています。自己決定理論とは、自己決定を軸に外発的動機づけから内発的動機づけ、他律から自律に変えていく因果律を理論化したものです。その段階を進めるには、自分の行動を自分で決めたいという『自律性』、自分の“できる”(優秀さ)を認められたいという『有能性』、周囲とのつながりを保ちたいという『関係性』の3つの心理的欲求をいずれも満たす必要があると言われています。そこでマルチスポーツは複数の種目から選べることで『自律性』を、運動を通じて成長を感じられることで『有能感』を、様々なスポーツに参加して様々な人と出会えることで『関係性』を与えるので、ウェルビーイングの向上につながるとされていますね。実際にニュージーランドでは『多様なスポーツに取り組めば体のバランスを保ちながら、アスリートとしてだけではなく人間としてのウェルビーイングを向上させられる』という考えが教育の根本にあって、国自体も世界幸福度報告書の2023年版で10位、世界競争力ランキングの2023年度で31位と、それぞれ47位、35位の日本より上に位置しています」
――自己決定理論は人材育成でもよく聞く考え方ですね。
「自己決定理論そのものは1970年代から提唱されていて、最近はスポーツコーチングでも取り上げられてきているんですけど、様々な実験・調査・研究を経て、その有用性がビジネスや軍事の分野でも証明され続けていますね。日本でも全国の2万人が調査されていて幸福度が高い人は学歴でもなく年収でもなく、自己決定の指標が高いというデータもあるくらいです。スポーツの現場でも特にキャプテンシーやリーダーシップでの有効性が示されていて、典型的な状況よりも例外的な状況でパフォーマンスをより引き出せるという証拠も報告されています。オールブラックスでも自己決定理論に基づいたデュアルマネージメントモデルが採用されていて、指導者は選手に意思決定権を与えて自主性を促しながら、選手と指導者の関係性でチームを二重管理して最終的に選手主導の意思決定に導くことで、潜在能力を最大限に引き出すアプローチを取っていますね。
ただ、マルチスポーツの経験者でその推進に賛同してくれている本田圭佑選手も話していましたが、慣れていないと『自己決定はそれなりに疲れる』と。だから自分で選ぶ機会や自分で決める機会を早いうちから増やしていかないといけない。それを促進させるのがマルチスポーツで、シーズンが終わるとラグビーゴールが学校のグラウンドから撤去されるニュージーランドのオールブラックスの選手も、『他のスポーツをやらなければラグビーは上手くならない』と口をそろえています。全員がラグビー以外のスポーツをたくさん経験しており、ラグビー代表とクリケット代表の二刀流として活躍したジェフ・ウィルソン選手のようなマルチスポーツアスリートもいるくらいですからね。他の選手も大学を卒業して名誉博士号や資格を取ったりするのが当たり前なんです」
――つまり、マルチスポーツを通じてウェルビーイングの向上とパフォーマンスの向上が両立できると。
「そうですね。だからマルチスポーツを政策化している国もあります。例えばカナダは7つの年齢・発達ステージに分けて、それぞれにおけるスポーツ活動の強度や関わり方を明確に示しているんですけど、ステージ1からステージ4(3歳から16歳)の段階でマルチスポーツを推奨しているんです。6歳から9歳の小学生低学年では1つのスポーツに特化させず、9歳から12歳の小学校高学年は1つのスポーツを週に3日したら他のスポーツをする。そして12歳から16歳は練習に他のスポーツを取り入れることを推奨しています。この『長期競技者養成モデル(Long-Term Athlete Development:LTAD)』は2004年から始まっていて、カナダ代表がW杯に初めて出場したりと競技力向上にも繋がっていますけど、それだけではなくて生涯スポーツの趣旨が前面に出されるようになってきているんですよね」
部活動地域展開への解決策、経営学の新視点としての可能性
――カナダ代表DFのアルフォンソ・デイビス選手も陸上やバレーボールをしていたそうですね。日本ではマルチスポーツはどれくらい浸透しているのでしょうか?
……

Profile
足立 真俊
岐阜県出身。米ウィスコンシン大学でコミュニケーション学を専攻。卒業後は外資系OTAで働く傍ら、『フットボリスタ』を中心としたサッカーメディアで執筆・翻訳・編集の経験を積む。2019年5月より同誌編集部の一員に。プロフィール写真は本人。X:@fantaglandista