「日本サッカーの日本語化」はなぜ重要?“ポリバレント論争”が秘める闇

去る6月上旬、中島翔哉のW杯メンバー落選をめぐって「ポリバレント論争」というのが起きた。複数ポジションでプレーできるという意味なら、2列目ならどこでもこなせる中島はポリバレントな選手であり、西野監督の落選理由は矛盾しているのではないか――という疑問だ。しかし、そもそも「ポリバレント」という言葉の意味が共有されていないので、議論は空回りするばかり。イングランドやポルトガルで指導者経験を積み、奈良クラブのGMに就任することが発表された林舞輝氏が感じた、日本サッカーの発展を阻む闇とは。
「ポリバレントではなかった」――ポルトガルリーグで昨季10ゴール10アシストを叩き出し、ロシアW杯期待の星として注目されていた中島翔哉の不選出理由を、西野朗元日本代表監督は記者会見でこう述べた。この発言と様々な解釈により、オシム監督が日本サッカー界に輸入した「ポリバレント」というサッカー用語に再びスポットライトが当たることになった。
「ポリバレント」と「ユーティリティ」の違い
後に西野監督は「ポリバレント」を単に「複数ポジションをこなす」という意味で使っていたことを明言したが、この言葉を好んで使い日本に広めたオシム監督にとっては、おそらく単に「複数ポジションを担える」以上の意味があったと考えられる。
そもそも、ポリバレント(Polyvalent)は化学の分野で頻繁に使われる用語だ。日本語の専門用語に訳せば「多価」となり、イオンや塩基などの価数が複数あることを示す。他と結合できる手がたくさんある分子構造図を想像していただければ、イメージとしてわかりやすいだろう。語源までさかのぼると、polyはギリシャ語が由来の接頭辞で「多くの」「複数の」という意味を持ち、valentはもともとラテン語で「~の力を持つ」という意味だ。従って、語源からそのまま訳せば、「多くの種類の力を持つ」「複数の価値を持つ」と訳するのがふさわしいように思える。
この時点で、ポリバレントはいわゆる「ユーティリティ」とは少し違うことがわかるだろう。キーは、「複数の種類での繋がり・組み合わせが可能」ということだ。ただ位置を変えられるというだけでなく、その変化によりその選手の特性の生かし方や他選手との繋がりを変えられる、もっと言えばチームの戦い方そのものを変えられるような選手だ。「多機能型選手」や「多目的型選手」という言い方がそれほど外れない意訳の仕方になるかもしれない。代表的な日本の「ポリバレントな選手」として、オシム監督は阿部、今野、長谷部などの名前を挙げていた(『オシムの戦術』中央公論)。オシム監督はまさにこの点を突き詰めて、ポリバレントな選手たちによる臨機応変・変幻自在なサッカーを目指していたのだろう。
ちなみに、ポリバレントという言い方は主にロマン語圏や旧ユーゴ地域で使われることが多く、英語(イギリス)ではあまり耳馴染みのない言葉だ。念のためイギリス人のサッカー関係の友人に訊いてみたところあまりピンとこないようで、あるコーチからは「俺にはその言い方はtoo educated(教養が深過ぎる)」と返された。一方、ポルトガルやスペインではよく使われ、周りに訊くと「ポジションを変えることによって複数の機能を果たせる選手」というような趣旨の回答が最も多く、代表的な選手では「キミッヒ」という回答がダントツで多かった。ユーティリティとの違いを訊くと、あくまでユーティリティは「どこでもできる」という範囲でしかなく、どちらかと言うと、チームにケガ人が出た時や主力を休ませたい時にどこでも代わりを務められる使い勝手のいい「ベンチにいたら便利な選手」というようなイメージが強いようだ。代表的なユーティリティ・プレーヤーとして最も多かったのは「ミルナー」という答えだった。

「ビルドアップ」の意味を正しく言えますか?
しかし、ここで問題なのは、ポリバレントの言葉の意味の正しさうんぬんではない。別にポリバレントがユーティリティと同じ意味だろうと違う意味だろうと、単に「どこでもできる」という意味で広く使われたとしても、たいしたことではない。本当の問題は、同じ言葉を人によって違う意味で使ってしまっているということだ。ここに、現在の日本サッカーの大きな問題があると言っても過言ではないだろう。同じ言葉でも、チームや監督が代われば意味が変わるようでは、選手間・指導者間のサッカー理解・戦術理解に支障をきたすのは想像に難くない。
例えば、サッカー界でよく使われる「ビルドアップ」という言葉がある。だが、日本ではこの言葉はきちんと定義されていない。ある人は最後尾のエリアでボールを保持している時と定義するかもしれないし、ある人は相手の最初の守備ラインを突破する前の状態と述べるかもしれない。あるいは、味方FWにボールが渡るまで、という意味で使っている人もいるだろうし、何か他の意味で使っている人たちもたくさんいると思う。また、仮に「ビルドアップ」が最も想像しやすいであろう「最後尾のエリアでボールを保持している状態」だとして、その「最後尾」とは一体どこなのだろうか? 自陣の半分より後ろなのか、一体どこからどこを指して「最後尾のエリア」とするのか。
こういった専門用語のすれ違いが起きないよう、欧州ではこのような細かい言葉の定義を各サッカー協会がしっかり決めて一般化し、客観的な定義の下で使われるように指導している国が多い。例えばポルトガルであれば、ビルドアップは「Construção」または「Fase 3」と呼ばれ、ピッチを三分割した時の自分たちの守るゴールに一番近いエリアと定めている。さらに、指導者のためのテキストには、そのエリアでの攻撃時・守備時でのプレーの目的や原則、要求される能力なども細かく記されている。「ビルドアップ」に限らず、ポルトガルではこのような体系化・定義化されたサッカーおよびサッカー用語を、指導者ライセンス講習会等を通して全指導者が徹底的に学ぶことになっており、Construção(=組み立て)、Fase 3(フェーズ3)と言われれば、ポルトだろうとベンフィカであろうと田舎の小さな街クラブであろうと、ポルトガル全土のすべての指導者が頭の中に同じ絵を思い浮かべるだろう。結果、監督が代わろうと選手が他のクラブに行こうと、サッカーの基本的な定義や概念の違いでギャップが生まれたり、それによって理解の差が生じたりすることはない。

興味深いことに、このような用語はしばしば国によって違う定義を持つことがある。「ビルドアップ」で言えば、オランダサッカー協会は上記のポルトガルとはまったく別の定義を持っている。オランダでも明確な定義が定められており、ビルドアップは「ゴールキックを始点にシュートチャンスを作り出すまで」とされている(『怒鳴るだけのざんねんコーチにならないためのオランダ式サッカー分析』ソル・メディア)。同書の言葉を借りると、「オランダ国内ではどこでも、アヤックスでも小さな街クラブでもどこへ行ってもビルドアップと聞けばこの『ゴールキックを始点にシュートチャンスを作り出すまで』を想像する」という。ポルトガルと同じように指導者ライセンス取得の際にこの定義を叩き込まれ、「チームのレベルや場所を問わず全指導者の中で共有され統一される」というのも同じだ。
ここで「ビルドアップ」の定義としてどちらがふさわしい、ポルトガル方式とオランダ方式のどちらが正しい、などというのは論点ではない。筆者は正直に言ってしまえば、どちらでも良いと思う。ここで最も大切なことは、「しっかり客観的で普遍的な定義や意味を決める」と「その定義・一般化された考え方が全土で共有され統一されている」という2点である。
曖昧になりがちなサッカー用語をきちんと定義し意味を明確にし、草の根まで浸透させることが、この先の日本でのサッカーへの理解を深める上で大切なことではないだろうか。日本代表であろうと地方の学校の部活動であろうと、同じサッカー用語は同じ意味で使い、すべての選手・指導者の頭の中に同じイメージが浮かぶようにしなければならない。曖昧なまま抽象的に概念化されるのを避け、同じ言語で共通の認識を共有できれば、不要な誤解や意見のすれ違いを避けるのに役立ち、選手・指導者同士のコミュニケーションもより円滑に行うことができるだろう。
そうすれば、ポリバレントをめぐる西野監督とメディアと世間の反応のような、一つの言葉の意味を引き金に不必要な深読み合いや論争が起こることも減るはずだ。筆者が以前開いた講習会の中でのディスカッションでも、「バイタルエリア」の意味が個人個人でズレがあったために議論が噛み合わないということがあった。サッカーへの共通の認識と理解を深めていく過程でこのようなことが頻繁に起きては、日本サッカーの発展の阻害になるのは間違いないだろう。日本ではあまりにも多くの曖昧に使われているサッカー用語が多過ぎるように感じられる。
選手・監督だけでなく「用語」が世界に羽ばたく
ポリバレントに限らず、フラット3、インテンシティ、そして記憶に新しいデュエル……。今まで様々な外国人の選手・コーチ・監督などを通して多くの言葉が日本に持ち込まれてきたが、日本サッカー界がその都度それぞれの言葉の真意まで聞き取り奥深くまで理解してきたかと問われれば、疑問符が付くであろう。もう少し、日本サッカー全体がそのサッカー言語の本質を突き詰めるという試みを丁寧にすべきだったかもしれない。
サッカーの世界だけに限らない話だが、新しい言葉というものにはメディアもファンもすぐに惹かれるのは自然なことだ。そして、それはサッカーという巨大な学問の理解への新たな扉を開くきっかけにすることもできる。だが、耳慣れない言葉をありがたがって何となく理解した気になり、自然とあちらこちらで使われ始め、気が付けば中身が詰まっていない用語ばかりが氾濫してしまうようなら意味がない。このままでは曖昧な定義の上に曖昧な言葉が重っていき、曖昧なサッカーへの理解と曖昧なサッカー文化が作られてしまうことになりかねない。
表面上のサッカー文化と表面上のサッカーへの理解でも表面上は強くなる。だが、日本がこの先さらに深く突き進むならば、もっともっとサッカーを突き詰めて考え、一つひとつの現象を見直し、その考えを積み重ねていく文化が必要だ。
「日本がサッカーの解釈で不利になるのは、日本語化ができていないことが原因だと考えています。日本のスポーツ、例えば柔道であれば『大外刈り』『背負い投げ』という文字を見れば技を知らなくても漢字から推測できる。でも、サッカーでは『ピリオダイゼーション』と言われても、どういったものなのかわからない。英語ネイティブは“Periodization”という単語を見れば“Period ”という名詞をベースとして、動詞の“Periodize に変化し、そこからさらに名詞化していることが直感的に理解できます。日本の漢字と同じですよね。オシム監督は『日本サッカーの日本化』と言いましたが、私は『日本サッカーの日本語化』が求められていると感じています。例えばピリオダイゼーションではなく区分法とか。野球は明治時代に正岡子規先生がすでにそれをやっているんです。バッターは打者、ピッチャーは投手など外来語をイメージしやすい日本語に置き換えているんですね」
これは過去の私のインタビューからの引用だが、誤解されて伝わっている部分があるので補足させていただきたい。「日本サッカーの日本語化」とは、外来語をきちんとわかりやすい日本語に訳しましょう、というような単純な話ではない(それも非常に大事な作業であることは間違いないが)。サッカーを日本語でもっと突き詰めて論理的に考えることで、曖昧になりがちな抽象的な概念の理解から脱却しなければならない、という意味だ。
もともと「言葉・言語」と「理論・論理」は古代ギリシャで同じ「ロゴス」(「ロジック」の語源)という単語であった。言葉があるからこそ論理的な考えを組み立てられるし、逆もまた然りだ。論理的な思考の構築の過程で新たな言語が生まれる。従って、海外から新たな言葉が輸入されてくるだけでなく、サッカーを突き詰めて考え構築していく中で日本語で新たなサッカー用語が生まれ、さらにその言葉が海外へ輸出されるようになることこそ、真の意味での「日本サッカーの日本語化」であろう。
「ポジショナルプレー」「5レーン理論」「偽9番」……。そういった言葉が外国から入って来るのではなく、日本サッカーの構築の過程で日本発のオリジナルな用語が生まれ、それを海外の国々が学ぶために、それぞれの国の言語に訳そうと奮闘する(実際、今のヨーロッパの若い指導者は優れた理論はどこで生まれたかは関係なく、すぐに学び取り入れようとする)――そのような現象が起きたとしたら、それこそが日本が「サッカーを考えられる」国になったという証拠であり、世界で「サッカー先進国」として認められる時ではないだろうか。

Photos: Getty Images, Bongarts/Getty Images
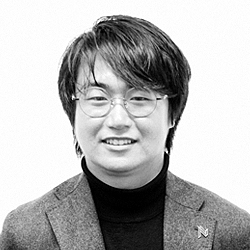
Profile
林 舞輝
1994年12月11日生まれ。イギリスの大学でスポーツ科学を専攻し、首席で卒業。在学中、チャールトンのアカデミー(U-10)とスクールでコーチ。2017年よりポルト大学スポーツ学部の大学院に進学。同時にポルトガル1部リーグに所属するボアビスタのBチームのアシスタントコーチを務める。モウリーニョが責任者・講師を務める指導者養成コースで学び、わずか23歳でJFLに所属する奈良クラブのGMに就任。2020年より同クラブの監督を務める。









