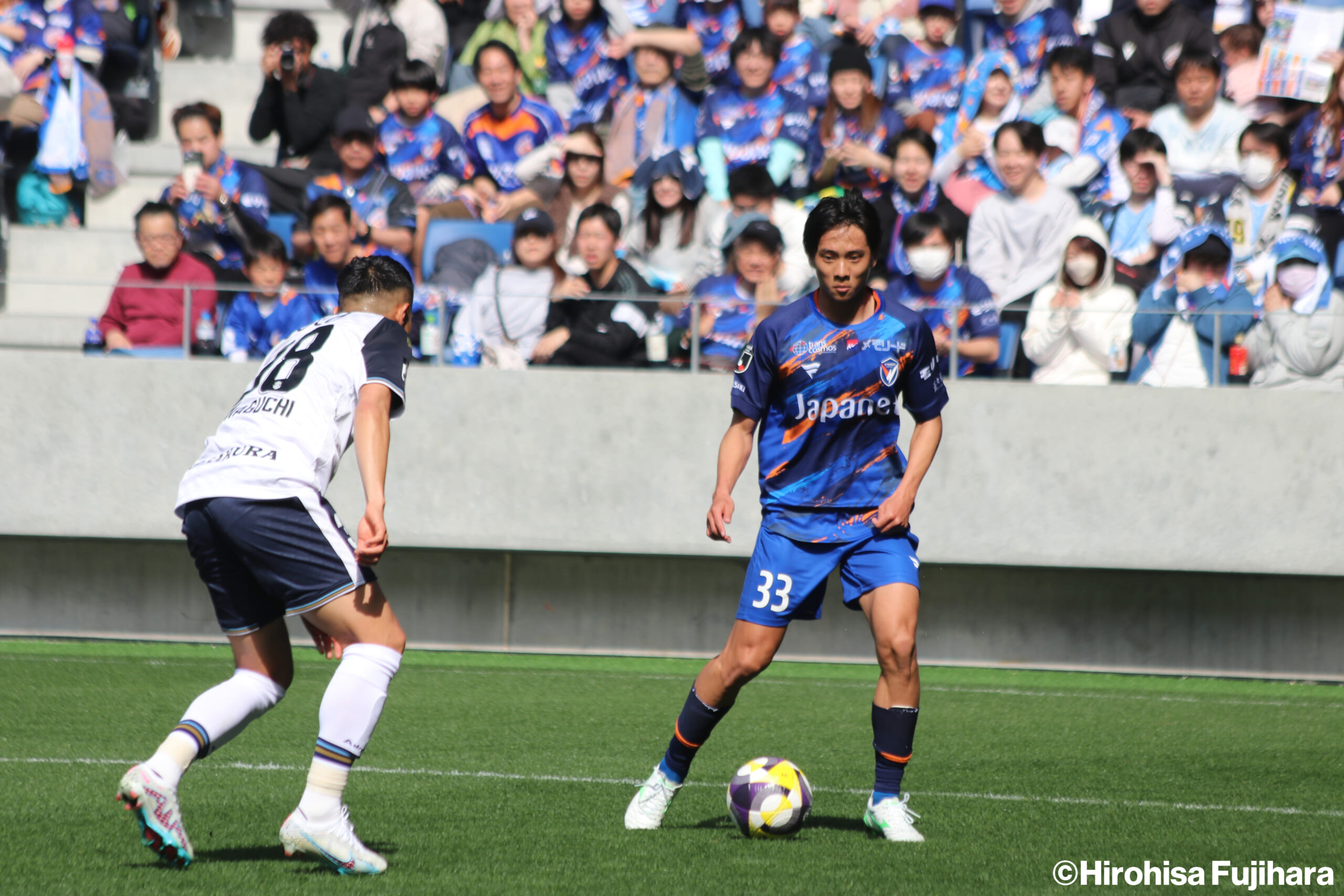「プレミアリーグとは5分以上の差がある」フットボール本部・小林祐三に聞く、JリーグがアクチュアルプレーイングタイムをKPIとして掲げた理由

サガン鳥栖のスポーツダイレクターを経て、今季からJリーグフットボール本部企画戦略ダイレクターに就任した小林祐三氏に、JリーグがアクチュアルプレーイングタイムをKPIとして掲げた理由について直撃した。なぜ年々数値が減少しているのか、「プレミアリーグとは5分以上の差がある」という現状、そして具体的なアクションプランを解説してもらおう。
サガン鳥栖SD→Jリーグ入りの経緯
――まず、サガン鳥栖のスポーツダイレクター(SD)を退任した後のことから聞いてもよろしいでしょうか?
「2024年4月15日に正式に退任が決まりました。残してしまった監督、選手、コーチングスタッフ、その他のクラブスタッフには最後まで一緒に戦うことができず申し訳なかったですし、最後の挨拶で『自分の力不足で大変申し訳なかった』と伝えました。その気持ちは今も変わっていません。同時に、自分としてはベストを尽くしてやるべきことをやり切ったという思いもありました」
――しばらくはフリーの期間だったんですか?
「Jリーグ入りが決まったのが10月末だったので、約半年間はフリーでした。辞めた時点でもともと半年は休もうと考えていました。現役時代からここまで家族との時間をあまり持てなかったので、子どもたちと一緒に旅行に行ったりしました。思えば、人生で夏休みのバカンスというものを経験したことがなかったので、かけがえのない時間だったかもしれません」
――半年経って、Jリーグからオファーが来たわけですね。
「はい。サガン鳥栖時代から野々村チェアマンには会場でお会いした際に声をかけていただいたり、お互いを認識している状態でした。フリーの期間に野々村チェアマンから声をかけていただき9月にお会いすることになり、そこでオファーをいただきました。1カ月間くらい考えて、お受けすることにしました。フットボール本部の窪田や樋口とも前職時代やSHC(一般財団法人スポーツヒューマンキャピタル)でやり取りする機会があり、いろいろなご縁がつながった形かもしれません」
――クラブでの仕事から制度設計側に回った理由は?
「大きく2つあります。1つは強化の仕事はサガン鳥栖でやり切った感があり、同じことは他でもできるでしょうし、その自信もありますが、別なチャレンジをしたいという思いがありました。もう1つはタイミングですね。Jリーグが30年経って、いろいろな制度が変わっていくフェーズだったので、それも魅力に感じました。特にフットボール面で自分が力になれるのではないかと思いました。同時に、強化責任者の立場でシーズン移行の意思決定の場に関わらせていただく中でビジネスレベルの高さを感じることが多く、ここで学べることも多いのではと考えました」
――近年は若手を中心とした海外移籍の加速によって、Jクラブの編成状況に大きな変化が起きています。クラブの強化責任者時代はこの状況に対して、どのように適応していこうと考えていましたか?
「マーケットの中で先手を打つことに尽きますね。『列の先頭に並ぶ』という言い方をしていましたが、獲得したい選手、スタッフには最初にオファーを出すことにこだわっていました。そのためには事前の準備が重要で、我々がどういうチーム、どういうコンセプトを持ってやっているのかを定めなければなりません。あとは現場との意思疎通のスピード感ですね。早く情報を共有し、ターゲットの優先順位を決める。近年のマーケットでは年々選手の価値が上がり、一方で我々の出せる金額は決まっている状況でした。そんな中で選んでもらうためには、『あなたが必要です』と早く伝えることと、コンセプトへの共感、その2点が大事になってきます。実際、サガン鳥栖よりもよい条件を提示されていた選手がうちに来てくれたことも多かったです」
――現場目線で既存のJリーグの制度に問題を感じていた部分はありましたか?
「制度自体には特になかったですね。廃止されたABC契約もサガン鳥栖の立場からすれば、横一線の交渉になるのであった方がありがたい制度でした。ただ、Jリーグの制度設計の会議に出席していた時は『各クラブの事情』と『日本サッカー全体の事情』の両方を意識して発言していました。日本サッカー、Jリーグ全体が前に進んでいかないと、結局クラブも前に進めなくなってしまうので」
――移籍金の安さが海外流出を後押ししているという意見もありますが、どう考えますか?
「誤解してほしくないのは、Jリーグは移籍金で稼ぐためのルール設計をしているわけではないことです。一番は、フットボールの水準を上げること。移籍金はその選手の価値とリーグの価値との掛け算だと思うので、Jリーグの価値が上がれば、そこでプレーする選手たちの価値も結果的に上がっていくことになります。もちろん、昔に比べて海外に挑戦するハードルは下がってきていますし、今の日本人選手の移籍金は相対的に見て安いと言われていますが、それが本当かどうかも含めて慎重に判断していかなければなりません。いずれにしても、リーグの価値を上げるのが自分の仕事で、移籍金を上げるための制度を作るというのは考えていません」
最初のミッションは、審判部とのコミュニケーション強化
――ここからはJリーグでの仕事について聞かせてください。フットボール本部企画戦略ダイレクターに就任されたわけですが、実際に任されている役割は何でしょう?
「フットボールに関わることすべて、特にピッチ上に関する領域ですね。今は特にレフェリーとのコミュニケーションを進めています。フットボール面でのJFAとの窓口にもなっていますね」
――審判部はJFAの所属ですからね。
「これまでは審判のことだけでなく、Jリーグはフットボール面に関して積極的な発信はしていなかったようです。フットボールの領域はJFA、ビジネス・興行面はJリーグという棲み分けになっていた。これからはフットボールの領域でもJFAと密にコミュニケーションを取って、ゲームの質を上げていくというのが野々村チェアマンの方針でもあります。その中で元選手、元強化責任者という私の経験を活かせる部分もあるのではないかと考えています」
――フットボール本部で進めている審判に関する新たな動きについて教えてください。
「いくつかありますが、ここでは2つご紹介します。1つは昨シーズンまで19人だったプロフェッショナルレフェリーを今シーズン24人に増やしています。もう1つは試合手当を増額しました。プロフェッショナルレフェリー手当はなくなったのですが、その分VARがない中で負荷がかかるJ2やJ3のレフェリーの報酬を上げています。ただ、これらは入社した時点で決まっていたことで、私が偉そうに言うことではないですけど(笑)。いずれにしても、アクチュアルプレーイングタイム(以下APT)の議論も含めて、レフェリーの皆さんにJリーグの目指すものを伝えて、一緒に試合の質を上げていく取り組みをしていきたいと考えています」
アクチュアルプレーイングタイムを指標にした2つの理由
――今季のJリーグは今話に出てきたAPTを伸ばすことをKPIとして掲げていますが、その意図を教えてください。
「APTはレフェリーだけのKPIではありません。選手とレフェリー、そしてピッチ上に関わるすべての人のKPIです。その前提の上でAPTをKPIに掲げた理由を説明させていただきます。主に2つですね。
……

Profile
浅野 賀一
1980年、北海道釧路市生まれ。3年半のサラリーマン生活を経て、2005年からフリーランス活動を開始。2006年10月から海外サッカー専門誌『footballista』の創刊メンバーとして加わり、2015年8月から編集長を務める。西部謙司氏との共著に『戦術に関してはこの本が最高峰』(東邦出版)がある。