
2019-20以来となるプレミアリーグ制覇へ向け邁進するリバプール。好調の大きな要因となっているのが、名将ユルゲン・クロップを後を継いだアルネ・スロットの存在だ。「自分が理想とするシステムはない」と明言するオランダ人指揮官の指導力の根幹を成す、攻撃に関する10の原則を3回に分けて紹介する後編。
アルネ・スロット率いるリバプールがプレミアリーグで首位を快走しているのは、縦方向だけでなく横方向の攻め手も持っているからである。
引き続き2017年の『De Voetbaltrainer』誌におけるアルネ・スロットのインタビューを解読し、今回は横方向の原則についてクローズアップする。
Arne 👊 pic.twitter.com/mlzsW4Mja1
— Liverpool FC (@LFC) January 3, 2025
原則7:サイドでボールを持ったら、反対側のハーフスペースへボールを運ぶ
スロットは横方向の使い方について、ボールを持っている高さで一定の整理をしている。大まかに自陣、ハーフウェイライン前後、敵陣に分けて順に見ていくとしよう。
現代サッカーのプレスは、ボールを片方のサイドに誘導して「同サイド圧縮」することで相手の選択肢を奪う方法が一般的だ。
つまり、攻撃側のチームにとっては、SBがライン際でボールを持つ状況が多くなる。この同サイド圧縮からいかに抜け出すかが、ビルドアップの成否を握っている。
この問題に対してスロットが用意しているのは「サイドでボールを持ったら、反対側のハーフスペースへボールを運ぶ」という原則だ。
「ボールがサイドにある場合、できるだけ軸にボールを戻すことが重要で、特に反対側のハーフスペースへボールを運ぶことを意識する。相手が片方のサイドに追い込んできた時は、逆側のハーフスペースにスペースができやすいからだ」
例えば相手の同サイド圧縮を受け、右SBがボールを持つ状況になったとしよう。
相手FWと相手MFがこちらから見て右サイドに寄って来るので、左サイドのハーフスペースにスペースが生まれることが多い。
そこを狙わない手はない。右SBは内側に向かってボールを持ち運んでボランチ(もしくはCB)へバックパスし、そこから一気に左ハーフスペースを狙うのだ。
これは自陣エリア以外でも有効な原則だ。ハーフウェイラインでも、ファイナルサードでも、やはりボールと反対側のハーフスペースに空白が生まれやすい。横方向を使ううえで基礎になる原則である。
Arne 👋 pic.twitter.com/XBOE9Sd3Sr
— Liverpool FC (@LFC) December 29, 2024
原則8:ハーフスペースで前向きに持ったら反対側のバイタルから裏抜け
それではうまくハーフスペースにボールを運ぶことができたら、次は何を意識すべきだろう?
……
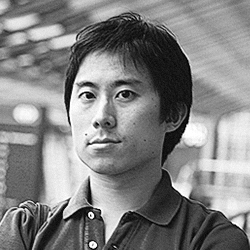
Profile
木崎 伸也
1975年1月3日、東京都出身。 02年W杯後、オランダ・ドイツで活動し、日本人選手を中心に欧州サッカーを取材した。現在は帰国し、Numberのほか、雑誌・新聞等に数多く寄稿している。














