
チーム戦術新解釈 攻⇄守4局面解説#1
5月14日に締め切られるロシアW杯予備登録メンバー(35人)提出前最後の代表戦となり、選手にとってもチームにとっても重要な意味を持つこの3月のインターナショナルマッチウィーク。着々と準備を進めている強豪国がどんな戦い方を志向しているのか、「攻撃」と「守備」だけでなく「攻から守への切り替え」「守から攻への切り替え」も含めた4局面にフォーカスして分析。各国の仕上がりをチェックする際の参考にしてほしい。
SPAIN
スペイン
予選:9勝1分0敗
3.6得点0.3失点(1試合平均)
監督:ジューレン・ロペテギ
51歳|スペイン
16年7月就任
ロペテギ監督になって最も変わったのがプレスへの意識。ボールロスト時のプレスはあまりに当たり前で、デル・ボスケ時代の末期には「習慣」を通り越し「おざなり」になっていた。サイドアタック中心だったから、ボールを失ってもただちに重大なピンチを招きにくい、という安心感もあったのだろう。だが、中央突破のリスクを負うロペテギはそんな弛緩を許さない。CFにもMFにも例外なく猛烈なプレスを命じる。相手の攻撃を遅らせるためではなく、ボールを奪い返しショートカウンターで急襲するためのプレスである。
プレスには「複数で同時に1人のボールホルダーに行っては駄目」という原則があるのだが、ロペテギが気にしている様子はない。その裏には、ショートパスを繋ぐサッカーをしている限り、ボールの周辺には味方が密集しているはずだ、という確信があり、フリーの選手が生まれるデメリットよりも、複数で高い確率でボールを奪い返せるメリットの方が大きい、という計算があるのだろう。

相手がバックパスをするとデル・ボスケ時代はその間に陣形を整えていたが、ロペテギはとにかくボールを追わせラインを上げさせる。後退の局面ですらボールへのプレスを強要しているほどだ。
守備から攻撃への切り替えでも、ロペテギの意識は「前」である。前監督体制ではプレスをかわすためバックパスとサイドチェンジがルーティーン化していたが、新監督は安易にボールを下げさせない。ボールを奪ったら奪った本人がまず局面の打開を図るべきという意識が徹底した結果、横走りのドリブルをよく目にするようになった。この横走りが、周囲がゴール前へ走り込んだり、ワンツーの中継点になる場所へ動いたりといった準備時間、間(ま)となるわけだから、決して無駄ではない。“急がば回れ”を地で行く、フリーポジション&フリーロールならではのプレーだ。
その一方で、前監督が苦心して根づかせようとしたCFへロングボールを送り込むカウンターパターンは、ロペテギの下でも失敗を重ねた挙句消滅しつつある。今後ジエゴ・コスタ(アトレティコ・マドリー)の招集とセットで復活するのか注目したい。
Photos: Getty Images
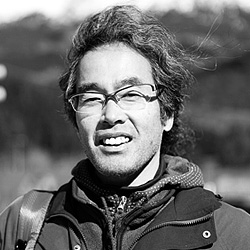
Profile
木村 浩嗣
編集者を経て94年にスペインへ。98年、99年と同国サッカー連盟の監督ライセンスを取得し少年チームを指導。06年の創刊時から務めた『footballista』編集長を15年7月に辞し、フリーに。17年にユース指導を休止する一方、映画関連の執筆に進出。グアルディオラ、イエロ、リージョ、パコ・へメス、ブトラゲーニョ、メンディリバル、セティエン、アベラルド、マルセリーノ、モンチ、エウセビオら一家言ある人へインタビュー経験多数。














