“第2の三笘”は現れるか。早稲田大学ア式蹴球部監督・外池大亮2021年大卒Jリーガーを語る

2020シーズンのJリーグでは筑波大学から川崎フロンターレに入団した三笘薫がリーグ戦13得点を記録し、ベストイレブンにも選出された。彼に代表されるように、近年は多くの大卒選手が目覚ましい活躍を見せている。
来たる2021シーズン、長らく大学サッカー界をリードしてきた早稲田大学ア式蹴球部から3人の選手がJの舞台へ活躍の場を移す。今回はチームを指揮する外池大亮監督に、早稲田からJへ挑む選手たちの成長、そして対戦した他大学の選手の印象などについて語ってもらった。
教え子たちの成長過程
――早稲田から3人がプロに加入しました。阿部隼人選手と山田晃士選手は2人そろってザスパクサツ群馬に行きましたね。まずは山田選手について伺いたいです。
「昨シーズンが始まる前に4年生全員と面談をしたのですが、そこで初めて山田が『プロに行きたいです』と口にしました。ただ、僕は『今のままじゃ無理じゃない?』と伝えました。当然、Jリーグに行ったらGKはサイズを見られます(山田選手は180cm)。サイズがなければ特別な能力がなければいけない。能力というのは防ぐ、止める、蹴る、繋ぐという部分ですね。それらを含めて、まだ良さを示せていませんでした。
だから今の段階では無理だ、と。そこで『そうですか。何かないですかね』と言われたので『ヤマダは声があるよね』と伝えました。声と言ってもいろいろなものがあるのですが、熱量や感受性みたいな部分を反映させてチームを繋ぐことができた。ゴールキーパーは最後尾に位置することを特性として、局面でのプレー機会以外の時間が山ほどある。そこに『声で繋げる』自身の強みを追求し、高めることでキーパーとしての価値や可能性を示すことはできるはず。そこが最低限だとは話しました。そうならないと注目してもらえないので」
――そこから変化はありましたか? 山田選手は4年になるまで試合に出ていませんでしたよね。
「GKコーチと話した際にも出てきたのが“勝たせられるGK”ということ。結局そこがないと最後の評価にはならないということを伝えました。そして、シーズン前に変化があったんです。紅白戦やトレーニングマッチを見ていて、山田が出ている時は負けていないことにある日、気づきました。例えば3本ゲームをやってGKをそれぞれ変えて臨んだ際、山田の出ていた時間は勝っている。彼はそれを積み上げた結果、信頼を得て正GKになりました。結果として優勝はできませんでしたが、勝たせるGKという役割は十分に果たせていたかと思います」
――ちなみに外池さんは現役時代に “勝たせられるGK”というのを感じた選手はいたのでしょうか?
「マリノスにいた時の川口能活からは感じましたね」
――次に、山田選手と同じく群馬に行く阿部隼人選手はどうでしょうか。
「彼は高校時代にクラブユース(サッカー選手権)を獲っていて、いい意味でも悪い意味でもその成功体験が基盤になっていました。それがあって早稲田の環境を受け入れられなかった部分があったと思います。でも、この社会で生きていくこととは? 社会で通用することとは?という部分に向き合い、その視座を身につけてから変わりました。
自分はこれだけをやり抜けば良いんだ、と思いサッカー界で1つの成功を収めたとて、それは社会的に見れば小さなものだということに気づいたんです。彼には『周りとの関係や調和を重んじながらやらないと、そこに繋がりを作れないんであれば、(主力としてプレーするのは)厳しいんじゃない?』と2年生の頃に伝えました。そこが重要だと気づいてから、変わりましたね。彼は卒業する時に『なんで自分がプロでやりたいのかがしっかり整理できた。最初は自信がなかったけど、この世界で生きていくことに対してのイメージができたから、チャレンジしたい』と言っており、変化が伺えました。彼はベースの部分1つひとつは優れているので、チームに適応して居場所と強みを発揮できれば十分やっていけるかなと思っています」
――ベースの能力というと、左足のキックですよね。
「あれはスペシャルですよね。FK、CKでチャンスを作ってくれます。一時期、[4-1-4-1]の右ウイング(WG)で使って、チームの攻撃時に左足で溜めを作って味方が押し上げる時間を作る役割を任せたことがありました。高い位置で左足のキックの精度も活きるし、技術も高くてハマっている感じはしました。ただ、彼が左サイドにこだわりたいと。プロでも左SBで勝負をすることになると思います」
――下級生の時からプロ志望だったのは鍬先祐弥選手(V・ファーレン長崎に加入)ですね。
「彼とは3年生の終わりに進路の話をしたのですが、そこで『僕はプロしか考えてないです』と。この学年で唯一でした。確かに、彼もずっと試合に出ていました。ただ、『クワがいたことで勝てた試合って、今年はほとんどなかったよね』と僕は伝えたんです。そこに対しての課題感をちゃんと持ってほしいと。アンカー、ど真ん中にいてチームを勝たせることができないんだとしたら、それは周りの人にけっこう伝わるよ、と。
そこをどう自分に落とし込むかが重要だとも言いました。自分のストロングやウィークのところと向き合って、勝つためにその自分のストロングをどう適用していくか。この道筋を描けるようになってほしいと思う中、彼も自身を変化させられるようになりました。自分がゲームの主役になるためのイメージを描いてピッチに立っているのが伝わりましたね」
――鍬崎選手はずっとアンカーでしたけど、今年は[4-1-4-1]のシャドーで使われていましたよね。そこでどういう形でアピールや変化を見せていましたか?
「やっぱり、クワの良さが見えるのは守備の時。ただ、プロに行くためにはただ守備ができる選手じゃなくて、“どういう守備ができるか”という部分がポイントになると伝えたんです。チームとして前からプレッシャーをかけた時に、網をかけにいって奪い取れる力があって、高い位置で奪えればショートカウンターの起点にもなる。そういう、攻撃に繋がる守備という意味ではシャドーが良いんじゃないか?という話をしました。
実際、[4-1-4-1]の前の2シャドーにおいてうまく前からはめる中で、彼が守備のスイッチになりながら、かつ奪い取るところまでやり切ってくれました。高い位置であれをやってくれることは凄く意味があったと思いますし、昨シーズンの早稲田のショートカウンターの象徴でした」
――となると、彼がいなくなって今年に響きそうですね。
「まさにそうです。今年、あの場面はどう作らせるかな?と考えたら、形を変えないと難しいなと思っているぐらいですね。それくらい彼の存在は大きかったです。結局、公式戦でもクワがいる試合といない試合では全然違っていました」

他大学卒Jリーガーの印象
――対戦相手について聞きたいのですが、明治大学の小柏剛は4年間、試合に出ていて苦しめられた部分があると思います。
……
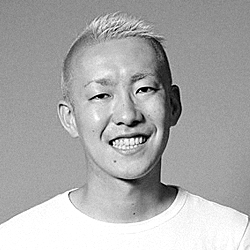
Profile
竹中 玲央奈
“現場主義”を貫く1989年生まれのロンドン世代。大学在学時に風間八宏率いる筑波大学に魅せられ取材活動を開始。2012年から2016年までサッカー専門誌『エル・ゴラッソ 』で湘南と川崎Fを担当し、以後は大学サッカーを中心に中学、高校、女子と幅広い現場に足を運ぶ。㈱Link Sports スポーツデジタルマーケティング部部長。複数の自社メディアや外部スポーツコンテンツ・広告の制作にも携わる。愛するクラブはヴェルダー・ブレーメン。









